二十四節気新・定番。


第1回|
第2回|
第3回|
第4回|
第5回|
第6回|
第7回|
第8回|
第9回|
第10回|
第11回|
第12回|
第13回|
第14回|
第15回|
第16回|
第17回|
第18回|
第19回|
第20回|
第21回|
第22回|
第23回|
第24回|
第25回|
第26回|
第27回|
第28回|
第29回|
第30回|
第31回|
第32回|
第33回|
第34回|
第35回|
第36回|
第37回|
第38回|
第39回|
第40回|
第41回|
第42回|
第43回|
第44回|
第45回|
第46回|
第47回|
第48回|
第49回|
第50回|
第51回|
第52回|
第53回|
第54回|
第55回|
第56回|
第57回|
第58回|
第59回|
第60回|
第61回|
第62回|
第63回|
第64回|
第65回|
第66回|
第67回|
第68回|
第69回|
第70回|
第71回|
第72回|
第73回|
第74回|
第75回|
第76回|
第77回|
第78回|
第79回|
第80回|
第81回|
第82回|
第83回|
第84回|
第85回|
第86回|
第87回|
第88回|
第89回|
第90回|
第91回|
第92回|
2020.11.27
F.I.N.的新語辞典
隔週でひとつ、F.I.N.編集部が未来の定番になると予想する言葉を取り上げて、その言葉に精通するプロの見解と合わせながら、新しい未来の考え方を紐解いていきます。今回は「逆レコメンド」をご紹介します。
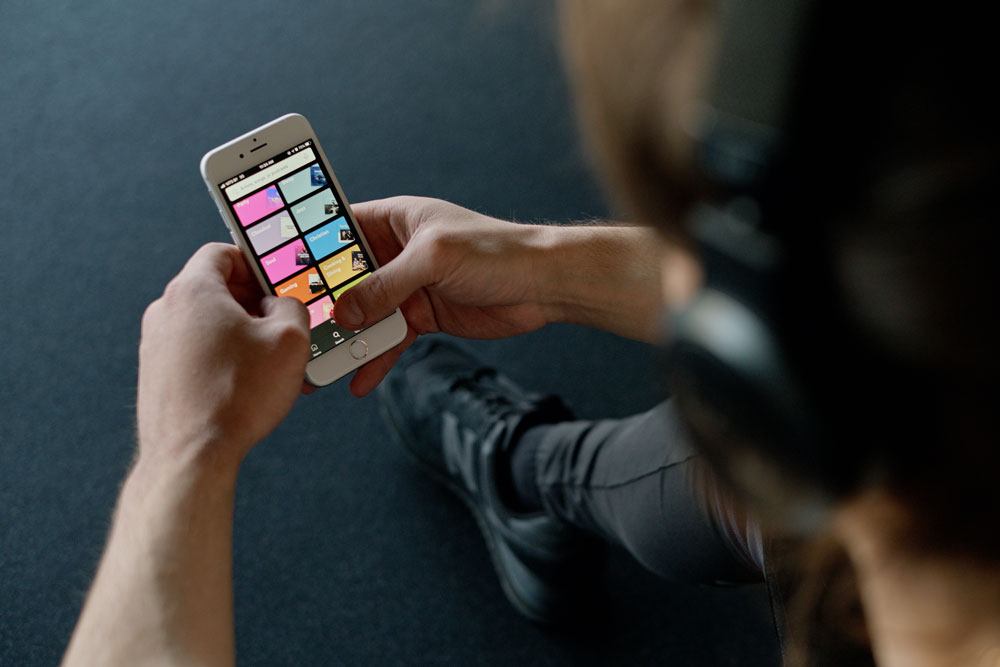
逆レコメンド【ぎゃくれこめんど/Preference elicitation】
ユーザーの検索ワードやサイトの閲覧履歴から分析し、好きなものを提示してくれる通常のレコメンドシステムの逆で、興味関心はあるがそれに気づいていないものや、あえて日頃購入しないものをおすすめしてくれる機能のこと。
「ECサイトなどで買い物をするときに、『あなたにおすすめ』や『この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています』という表示を見たことがあると思います。この仕組みをレコメンド機能と呼びます。逆レコメンドはこの進化版で、自分では気づかないような商品を紹介してくれるサービスです」。そう話すのは、株式会社電通の「未来予測支援ラボ(https://dentsu-fsl.jp)」で未来を見据えたアイディアの発想・提案を行っている立木学之さん。逆レコメンドという概念は、レコメンドシステムの持つ課題から生まれたそう。
「レコメンド機能では、ユーザーの見たいものしか見えなくなることで、興味関心の幅が狭まっていく『フィルターバブル』という現象が起きます。IT革命以前は、実際にお店に行くことで、それまで関心のなかった商品に偶然出会うという“セレンディピティ”が起こり得ましたが、デジタルの世界では関心のある情報しか目に入らなくなり、そういった偶然の出会いというものが担保されなくなってきています」。
その流れから一部の先端的なテクノロジーを採り入れている企業では、数年前から逆レコメンド機能を採用するところが多くなっています。例えば音楽ストリーミングサービスの「Spotify(スポティファイ)」は、性別や年代などの属性をもとにビッグデータから解析し、これまでに出会ったことのないような曲をすすめるといったアルゴリズムを使用しています。仮に、ユーザーが30代の日本人女性である場合、物心が付く前の1990年代にヒットしたアメリカンポップスを勧めてくるというような仕組みです。
「何か新しいものを発見したときに、脳は快感を覚えるそうです。人の心身の健康のためにも、興味や関心にも多様性があることが重要です。ユーザーエクスペリエンスの質を高めるのも、デジタル時代における企業の役割ではないでしょうか」。
第1回|
第2回|
第3回|
第4回|
第5回|
第6回|
第7回|
第8回|
第9回|
第10回|
第11回|
第12回|
第13回|
第14回|
第15回|
第16回|
第17回|
第18回|
第19回|
第20回|
第21回|
第22回|
第23回|
第24回|
第25回|
第26回|
第27回|
第28回|
第29回|
第30回|
第31回|
第32回|
第33回|
第34回|
第35回|
第36回|
第37回|
第38回|
第39回|
第40回|
第41回|
第42回|
第43回|
第44回|
第45回|
第46回|
第47回|
第48回|
第49回|
第50回|
第51回|
第52回|
第53回|
第54回|
第55回|
第56回|
第57回|
第58回|
第59回|
第60回|
第61回|
第62回|
第63回|
第64回|
第65回|
第66回|
第67回|
第68回|
第69回|
第70回|
第71回|
第72回|
第73回|
第74回|
第75回|
第76回|
第77回|
第78回|
第79回|
第80回|
第81回|
第82回|
第83回|
第84回|
第85回|
第86回|
第87回|
第88回|
第89回|
第90回|
第91回|
第92回|
二十四節気新・定番。
オムロン株式会社に聞いた、新しいテクノロジーとのニューノーマルな暮らし。<全2回>
目利きたちと考える、季節の新・定番習慣。<全10回>
オムロン株式会社に聞いた、新しいテクノロジーとのニューノーマルな暮らし。<全2回>
18歳の噺家・桂枝之進さんが考える新しい落語論。<全2回>
これからの5年で変わるもの、変わらないもの。<全8回>
二十四節気新・定番。
オムロン株式会社に聞いた、新しいテクノロジーとのニューノーマルな暮らし。<全2回>
目利きたちと考える、季節の新・定番習慣。<全10回>
オムロン株式会社に聞いた、新しいテクノロジーとのニューノーマルな暮らし。<全2回>
18歳の噺家・桂枝之進さんが考える新しい落語論。<全2回>
これからの5年で変わるもの、変わらないもの。<全8回>