

第1回|
第2回|
第3回|
第4回|
第5回|
第6回|
第7回|
第8回|
第9回|
第10回|
第11回|
第12回|
第13回|
第14回|
第15回|
第16回|
第17回|
第18回|
第19回|
第20回|
第21回|
第22回|
第23回|
第24回|
第25回|
第26回|
第27回|
第28回|
第29回|
第30回|
第31回|
第32回|
第33回|
第34回|
第35回|
第36回|
第37回|
第38回|
第39回|
第40回|
第41回|
第42回|
第43回|
第44回|
第45回|
第46回|
第47回|
第48回|
第49回|
第50回|
第51回|
第52回|
第53回|
第54回|
第55回|
第56回|
第57回|
第58回|
第59回|
第60回|
第61回|
第62回|
第63回|
第64回|
第65回|
第66回|
第67回|
第68回|
第69回|
第70回|
第71回|
第72回|
第73回|
第74回|
第75回|
第76回|
第77回|
第78回|
第79回|
第80回|
第81回|
第82回|
第83回|
第84回|
第85回|
第86回|
第87回|
第88回|
第89回|
第90回|
第91回|
第92回|
第93回|
第94回|
第95回|
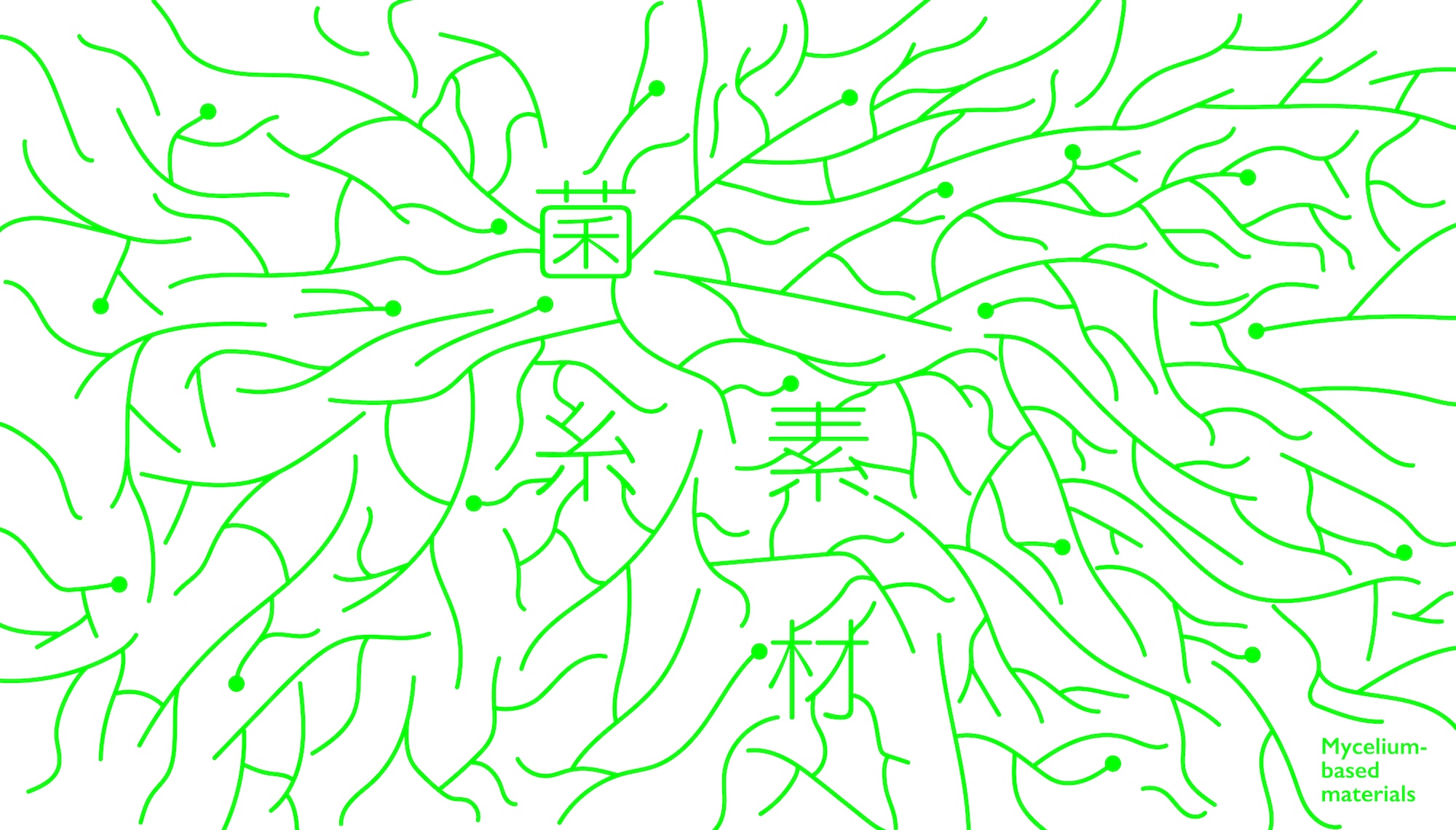
F.I.N.編集部が未来の定番になると予想する言葉を取り上げて、その言葉に精通するプロの見解と合わせながら、新しい未来の考え方をひも解いていきます。今回は「菌糸素材」をご紹介します。
(文:大芦実穂)
菌糸素材【きんし・そざい/Mycelium-based materials】
キノコの菌糸体(マイセリウム)を利用した生物由来の新素材。家畜の飼育や食肉加工を伴わず、環境負荷を低減できる点が特徴。また、生分解して土に還ることから、持続可能な素材として期待されている。この技術の先駆者である、カリフォルニアの〈Bolt Threads(ボルトスレッズ)〉が開発した「Mylo™(マイロ)」が有名。近年は、日本国内でも長野県のキノコ生産技術を活用した研究などが進んでいる。
〈エルメス〉、〈バレンシアガ〉、〈ステラ・マッカートニー〉、〈アディダス〉など、世界的に有名なファッションブランドがこぞって取り入れている菌糸素材。その可能性と社会的背景について、『皮革とブランド──変化するファッション倫理』(岩波新書)の著者であり駒澤大学教授の西村祐子(にしむら・ゆうこ)さんにお話を伺いました。
2013年頃から本格的に研究が進められてきたその背景には、人々の天然皮革に対する問題意識が関係していると西村さんは話します。
「19世紀末の欧州で、倫理的観点から動物由来の食品を避ける動きが生まれ、環境配慮を唱える人道主義へと発展していきました。ただ、当時はまだ倫理的消費を支える生産体制が未成熟だったため、人々が求めるような革に代わる植物由来の商品はありませんでした。しかし、20世紀から21世紀にかけて、バイオテクノロジーが目覚ましい発展を遂げ、植物由来の素材がどんどん生み出されるようになりました」
このような状況下で、菌糸素材が「マッシュルームレザー」として生み出され、日本でも生産がはじまりました。いわゆる「エコ・レザー」あるいは「ヴィーガンレザー」と呼ばれるものにはコルクやパイナップルの茎を使った素材もあります。しかし、これらを従来の皮革と区別するため、2024年3月に日本産業規格(JIS)から「『革』『レザー』と呼ぶのは動物由来の素材に限定する」という発表があり、国際規格ISOや欧州統一規格EN15987に基づいて、2024年4月1日から欧州でも同様の規制が適用されるようになっています。革ではない代替品を「レザー」と呼ぶ危険性について、西村さんは次のように話します。
「世の中で『ヴィーガン・レザー』『エコ・レザー』などといわれているものは、植物由来といいながら、製造過程でプラスチックを混ぜていることが多いです。プラスチックは土に還りません。これでは、とてもサステナブルとはいえません。ですから、皮革業界は非動物由来の素材とは一線を画し、それらのまがいものと同列に扱われるのを拒んでいます。とはいえ、菌糸素材には長所があります。プラスチックなどの土に還らない素材は含まれておらず、100%生分解が可能です」
他にはどんなところが優れているのでしょうか?
「菌糸素材の長所は4つ挙げられます。1つ目はなんといっても生分解が可能で土に還ること。廃棄後の環境負荷が少なくて済みます。2つ目には皮革と異なり、製造過程で貴重な水の使用を抑えられることです。動物の皮を革にするときに大量に消費される水や化学薬品の使用を抑えられ、環境にやさしい点もあげられます。3つ目は素材としての多様性があることです。柔らかく薄い為、手触りもよく、衣類はもちろん、バッグや壁紙、ヨガマットなど、幅広い製品に活用が可能です。4つ目は軽量であること。天然皮革と比べて軽く、持ち運びやすいのです」

〈ステラ・マッカートニー〉が2022年に発売した菌糸素材を用いたバッグ
このように聞くと、利点ばかりのように思えますが、実はまだ課題もあるといいます。
「まず、耐久性の問題です。天然皮革や合成皮革に比べて摩耗や水に弱いという欠点があります。次に高コストであること。培養や加工体制がまだ確立途上のため、皮革に比べると製造コストが高くなります。また、大量生産が難しいという問題があります。天然素材ならではの個体差があるため、均一な品質を確保しにくい点も課題としてあげられるかもしれません」
では、5年先、10年先、天然皮革や菌糸素材を取り巻く環境はどのように変化しているのでしょうか。西村さんの見解を聞きました。
「天然皮革は依然として市場で重要な位置を占めると思います。一方で、植物や菌糸由来の素材も市場では2桁台の成長をしており、2022年から2030年にかけて、年平均成長率が37.5%に達するという予測もあります。つまり、商業的には『有望な素材』と判断されているのです。しかし、その際に注意しなければならないのは、本当に環境にいい製品かどうかを見極めることです。せっかく生分解できる素材でつくられているのに、仕上がりをよくみせ、皮革なみに防水加工しようと考えて、プラスチックでコーティングしたりすれば、環境負荷はかえって高まります。菌糸素材にポリウレタンや塩化ビニルなどを混ぜて固めるようなチープな製品では、環境にかえって悪影響をもたらします。環境負荷の高いまがいものが出回ってしまっては、元も子もありません。購入するときにはその点を注視していく必要があるでしょう」。
第1回|
第2回|
第3回|
第4回|
第5回|
第6回|
第7回|
第8回|
第9回|
第10回|
第11回|
第12回|
第13回|
第14回|
第15回|
第16回|
第17回|
第18回|
第19回|
第20回|
第21回|
第22回|
第23回|
第24回|
第25回|
第26回|
第27回|
第28回|
第29回|
第30回|
第31回|
第32回|
第33回|
第34回|
第35回|
第36回|
第37回|
第38回|
第39回|
第40回|
第41回|
第42回|
第43回|
第44回|
第45回|
第46回|
第47回|
第48回|
第49回|
第50回|
第51回|
第52回|
第53回|
第54回|
第55回|
第56回|
第57回|
第58回|
第59回|
第60回|
第61回|
第62回|
第63回|
第64回|
第65回|
第66回|
第67回|
第68回|
第69回|
第70回|
第71回|
第72回|
第73回|
第74回|
第75回|
第76回|
第77回|
第78回|
第79回|
第80回|
第81回|
第82回|
第83回|
第84回|
第85回|
第86回|
第87回|
第88回|
第89回|
第90回|
第91回|
第92回|
第93回|
第94回|
第95回|