地元の見る目を変えた47人。


2021.04.08
5年先の未来、私たちの住まいはどうなっているのでしょうか? 人々のライフスタイルや働き方が多様化するなか、この数年にも多拠点生活やアドレスホッパーなど、次々と新たな居住様式が注目を集めました。しかし新型コロナのもたらした大きな変化により、私たちは途端に、数ヶ月先の暮らしぶりさえ予見できなくなりました。今回、「未来の住まいの新定番」を探るために、私たちは住まいの原点である「家/ホーム」そのものについて、改めて考えてみることにしました。
記事には2人のゲストをお招きします。「ホームフル」という新しい概念を通して、人々が「家」の機能を都市のなかに分散させていく現象を考察してきた、編集者の石神俊大さん。そして現代日本の住宅政策や住まいについて研究を重ねてこられた、神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授・住宅研究者の平山洋介さん。私たちの未来の「ホーム」をめぐる、2人の賢人による対話が始まります。

石神俊大
編集者/ライター。1989年、東京生まれ。おとめ座。『WIRED』日本版編集部を経て、現在は編集者/ライターとして書籍や雑誌の編集、企業コンテンツの編集・ライティングなどを手がける。また、自身のライフワークとして「ホームフル」にまつわる思索を、様々な媒体や形式で展開している。
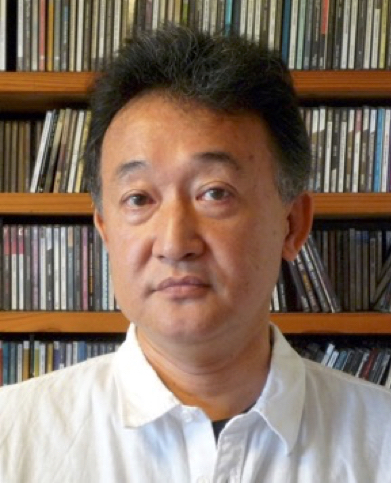
平山洋介
神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授。著書に『マイホームの彼方に』(筑摩書房2020年)、『「仮住まい」と戦後日本』(青土社2020年)、『都市の条件』(NTT出版2011年)、Housing in Post-Growth Society (Routledge, 2018, 共著)など。
「ホームフル」という新概念を起点に
日本人の「ホーム」の歴史をたどる
今回、未来の住まいの新定番を探究するにあたって、まずは石神俊大さんが提唱する「ホームフル」という新概念を起点に議論を始めました。
「“ホームフル”の発端となったのは、30代独身男性の自分が東京の暮らしのなかで感じた、家の機能が都市のなかへ分散していく感覚でした。家の用途は寝室程度に限られ、仕事はwi-fiが通っているカフェへ行き、お風呂はサウナや銭湯へ行く。モノも最低限しか持たず、必要があればコンビニやスーパーで買い揃える。家の機能をどんどん分散し、遍在させていくライフスタイルに“ホームフル”という造語をあてて考え始めたのが、3年前くらいのことです」(石神さん)
時を同じくして、家を持たず転々と移動しながら暮らすアドレスホッパー(*1)が生まれたり、Airbnb(*2)が人々の家の感覚を更新したりする状況が重なります。私たちと、家。その距離感や位置づけが変わってきていました。
*1 アドレスホッパー… 定住する家を持たずに、移動しながら生活する人々や生き方のこと
*2 Airbnb… エアビーアンドビー。空き部屋と部屋を借りたい旅人とをマッチングする新しい民泊サービス
「マスメディアはこうしたライフスタイルを、“新しくクールなもの”として提示しますが、僕はどこか危険なものでもあると感じています。この現象を前に、自分たちはどのように生きていくのが良いか? そうした問題意識を“ホームフル”という言葉に込めていました」(石神さん)
実はこのように“住宅ではなく都市に住む”という概念は、数十年前から存在していたものだと平山さんは言います。たとえば戦後の東京や大阪に量産された木造アパートは、そもそも狭く、ほとんど寝るためだけの空間として提供され、その住人たちは銭湯に通い、行きつけの定食屋や飲み屋をもつなど、都市のなかに生活の拠点を置いていました。
「東孝光の『塔の家(1966)』は象徴的でした。都心の20平方メートルという狭小な敷地に建てられた五階建てで、必要最低限の生活機能だけを備えていました。本が必要なら図書館へ借りに行き、友達とは喫茶店で会い、家族との団欒の場も戸外に求めればよい。ここで示唆されたのは、まさしく“都市に住む”という生活のあり方でした。
そしてこれは、当時の社会が理想としていた、郊外に一戸建てのマイホームを建てることへの対案でもありました。家族のだんらんと子育ての場としてつくられ、また、盆と正月には親族が集合する場となるような家。それはさらに、さまざまな家電製品から応接セット、誰にも読まれない大部の百科事典まで、大量の物財をためこむ貯蔵庫として、物質的な豊かさを象徴するものでもありました。こうした“重い”住まいに対して、もっと“軽く”都市に住むことの提案です」(平山さん)
時代ごとに変わりゆく「ホーム」観
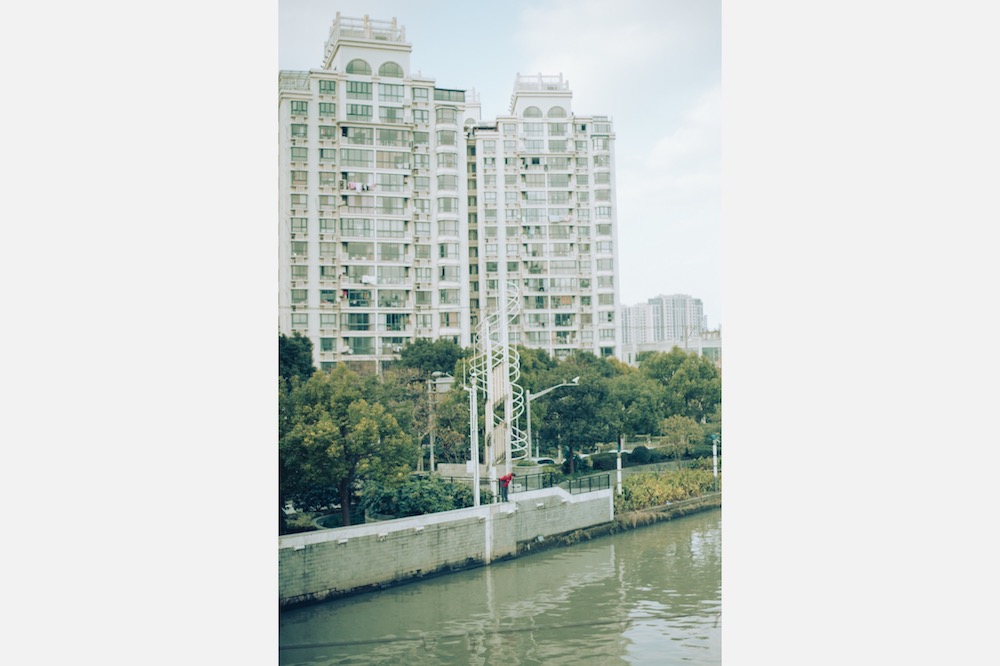
自己所有の住宅に住む世帯の割合は、現在およそ60%程度。戦前の都市部では約20%にすぎませんでした。では、戦後に急増した持ち家、マイホームは何を意味したのでしょうか。
「戦後、住宅の所有が含意したのは“解放”でした。終戦直後の農地開放は、地主制度を解体し、多数の自作農を生みだしました。これに似た変化として、都市地域では、多くの人たちが持ち家を建て、あるいは買い、家主と家賃支払いから自らを解放しました。並行して、“独立・自立した世帯”をつくる人たちが増えた。それは、結婚と子育てのユニットで、出身家族・階層・地域から自分を切り離す意味をもっていました。戦後社会は、少なくとも建前の上では“出自を問わない”社会です。それを支えたのが、結婚と持ち家という制度、その制度に立脚した“マイホームを所有する独立・自立世帯”でした」(平山さん)
しかし就労の不安定化、未婚の増大、女性就労率の上昇などの社会変化から、21世紀には独立・自立世帯というユニットの成立の基盤が揺らぎました。
「前世紀の末から、世帯単位の社会が崩れ、一方で人びとの単身化が進み、他方で家族化が顕著になります。単身者、未婚者が増え、親元に住み続ける世帯内単身者も増えた。これが単身化。同時に、どういう家族の出身なのかが再び重要になる、家族化の傾向が現れました。2つは逆向きの変化でありながら、“独立・自立した世帯”を減らす点で、同じ結果を生みます。
家族化が顕著なのは、住宅と教育の領域です。持ち家取得の基本パターンは、若い夫婦が独立して住宅を買うことでした。しかし、親の持ち家率が高くなった現在では、親世代の住宅を受けつぐ人たちが増え、子どもの住宅購入を親が助けるケースも増大します。親の社会階層が、子世代の住宅事情に影響するようになりました。教育領域では、たとえば、大学生に関する調査の結果は、東大生の親御さんの所得が最も高いという実態を明らかにしています。良い大学に入るには、小さい頃からの塾通いなど、親の助けなしには難しい状況がある。さらに論点は、所得の高低だけではありません。家庭に本がいっぱいあったのか、たまにはコンサートへ連れていってもらえたか……。ブルデューのハビトゥス(*3)概念が示唆するように、家族の文化資本が子どもの性向に与える影響は大きく、それはそのまま彼らの住宅観にも関係します。人生の“家族化”には、“出自を問う”社会の再出現が反映しています」(平山さん)
*3 ハビトゥス…過去の経験的蓄積によってかたちづくられる、無自覚の習慣や知覚・思考・行為を生み出す性向。社会学者ピエール・プルデューらが用いた。
「僕自身、東京生まれ東京育ちで、小さい頃から塾に通って東京の大学に入った、まさしくお話の典型のような人間です。経済的にも文化的にも家族から与えられたものは無視できませんし、一人暮らしをはじめたときも、家族から“解放を勝ち取った”という感覚ではありませんでした。
お話を聞きながら、最近見た2つの日本映画のことを思い出していました。映画『あのこは貴族』(*4)で見られた、東京で暮らす人々に潜む出自の格差。あるいは『花束みたいな恋をした』(*5)で見られた、地方から上京してきた男性主人公と、都会の大企業で働く両親のもとで育ったヒロインのあいだに生まれる価値観のギャップ。こうした家族や出自に起因する感覚は、僕より下の世代の子たちの“ホーム”観に、大きく影響していくのかもしれません」(石神さん)
*4 「あのこは貴族」…2020年の日本映画。東京の上流家庭で育った女性と、東京に必死でしがみつく地方出身の女性。2人の女性の姿を通して階層化する現代社会を描いた。岨手由貴子監督、山内マリコ原作。
*5 「花束みたいな恋をした」…2021年の日本映画。偶然に出会った大学生の男女2人が、文化的嗜好の一致から強く惹かれ合う。同棲を開始して就職を経験する5年間のうちに生まれる価値観の変化を描く。土井裕泰監督、坂元裕二脚本。
帰ることが、そこを「ホーム」たらしめる
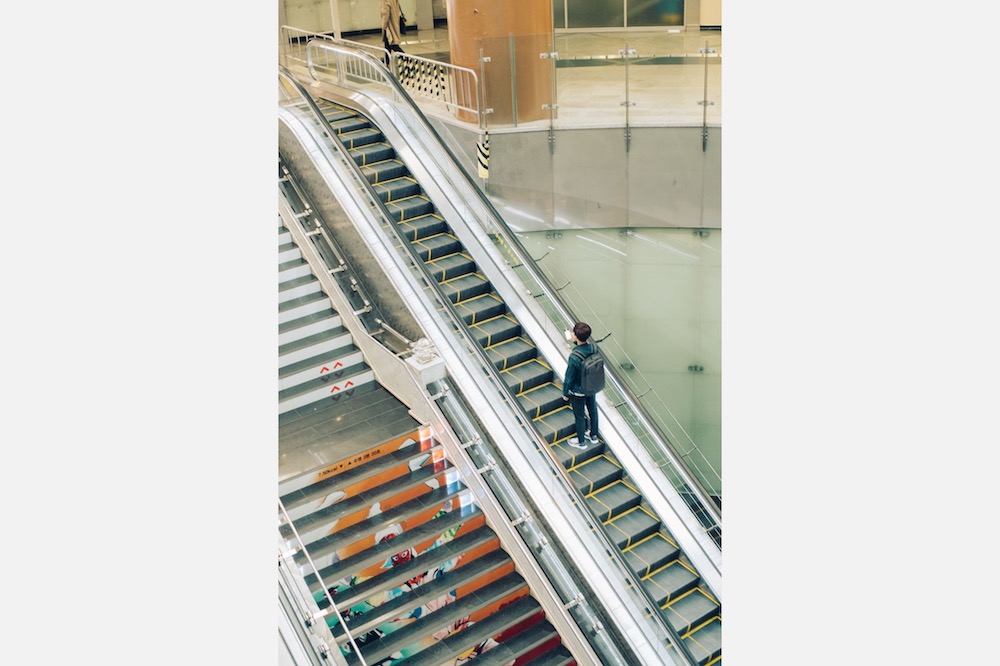
「石神さんが“ホームフル”にまつわる記事でも書かれていたように、出先から帰るからこそ、住まいは“ホーム”になります。グローバル化が進む世界で、多くの人々が動き回っているイメージがありますが、いま、コロナの影響で、人々の動きの量は急減しています。さらに、特に若い世代では、結婚、出産などの減少に関連して、転居が大幅に減っていた。地元志向が強まったという見方もあります。若い世代に増えたのは“移動しない人生”です。このように人々の動きが減るとすると、それが私たちの“ホーム”にどう影響するかを、見ておく必要があります」(平山さん)
かつて東京とは、地方の若者にとって“出ていく先の場所”であり、知らない人同士が集まって住むための空間でした。ところが現在の東京では、8割近くの人が東京出身です。グローバリゼーションの最先端都市である東京に、生まれた場所のことしか知らない人が増えています。
「東京の人たちは、実は、あまり動かない。世界の中心を占める東京から、わざわざ離れる必要がありません。日常生活は東京のなかで展開しますし、地方にわざわざ引っ越す人はごく少ない。そのとき東京は、東京生まれの人の“ホーム”になりえるのか? 生まれ育った場所は、そこを離れてはじめて“故郷”になります。20世紀には、多くの人びとにとって、故郷と、出ていく先の都市という2つの空間がありました。もしこれから、生まれ育った場所にずっと残る人が増えるならば、故郷と都市という概念自体も、変化していくのかもしれません」(平山さん)
「東京以外の街で暮らしたこともなく、実家も東京から近いため帰省体験も持たない自分には、ある種のコンプレックスのようなものがあります。帰るべき故郷がある人を羨むような気持ち、とでも言うのでしょうか。だからこそ自分は仕事で、毎月のように海外へ行くことを、意識的に続けていたのかもしれません」(石神さん)
私たちは、何のもとへ「帰る」のか
「帰る」を考えることは、人々の帰属先を考えることでもあります。20世紀後半の日本では、多数の人たちの主な帰属先は、家族と会社でした。
「会社は、社員と家族を同一視するほどに強力な帰属先でした。しかし21世紀前半の今、そこまで強い帰属意識を会社に抱く人は少ないでしょう。これからの若者は、果たしてどこを自分の帰属先や帰る場所とするのでしょうか。家族? それともお友達の集団でしょうか?」(平山さん)
都市論の世界では、大まかに分類すると、都市のなかでの親密な人間関係や所属先を重視する「コミュニティ派」と、独立した個人が生きていけるような都市のあり方を重視する「アーバン派」があると言われます。あるいは建築家クリストファー・アレグザンダー(*6)にならえば、建築とは帰属すべき「コミュニティ」と個人の「プライバシー」を両立させ、その関係を調整する技芸でもあります。いずれも、どちらか一方が正しい、ということにはなりません。
*6 クリストファー・アレグザンダー… ウィーン出身の建築家・都市計画家。単語を集めて詩や文章をつくるように、パターンを集めて建築やコミュニティを形成する「パタン・ランゲージ」理論を提唱した。
「都市や住まいのあり方として、これが唯一絶対重要な理想だと掲げられる時代ではなくなったのだと思います。コミュニティとアーバン。コミュニティとプライバシー。あるいは、定住と移動、安全と挑戦、所属と独立、グローバルとローカル・・・。重要なのは、どちらが正しいのか、ではなく、そうした考え方のフレームをもち、次に何が生まれるのかを探ることです。
今、人々はどんどん個人化しています。一人で独立していたいという希望がある。他方で、安全な帰属先なしに生きていけるのかといえば、それが可能なのはきわめて強い人間に限られる。ありきたりな表現になりますが、人間は一人では生きていけません。個人の自立を保ちながら、安心して帰属できる都市・空間をつくるとしたら、何をどうやってつくるべきか? これは重要な問いだと思います」(平山さん)
「21世紀に入って、色んなプラットフォームやサービスが整備され、社会は“一人で生きていける”ことをどんどん実現させていきました。しかしこの5年くらいで、そのこと自体もまた見直されています。それは都市や住まいの話題に限らず、近年よく耳にする“ケア”といったキーワードなどにも関わる視点だと思います。そのうえで、人とのつながりや絆といった情緒的な話だけに流されず、双方の良い面を共存させていける道を探る必要があるのかもしれません」(石神さん)
未来の住まいを考えるために必要なこと
私たちの常識や、理想とするライフスタイルは、メディアや言説によって作られ、さらに、どんどん商品化される。そこではいつでも立ち止まって考える姿勢が必要だと平山さんは言います。
「メディアでは日々、いろんな都市論が発表されます。研究者もメディアの人たちも、“尖ったこと”を言おうとする。それらはどれも、興味を引きつける、新しくて派手な話です。でも実際のところ、住宅や生活というものには、保守的な部分があることを忘れてはいけません。今でも半数以上の世帯は家を買うし、多くの人が結婚して子どもを育て続けています。社会学者の鈴木栄太郎(*7)は、研究者は社会のなかの病理や新しい現象ばかりに着目しがちであると指摘しました。そうではなく、ごく普通に暮らしている人々を、きちんと見なくてはいけない。普通といっても画一的でなく、より多様になった点を忘れるべきではありませんし、そもそも普通とは何なのかという重要な論点があります。そういう“普通”は、メディアのニュースにはならないかもしれませんが、そこを看過せぬよう意識することが大切です」(平山さん)
*7 鈴木栄太郎… 農村社会学、都市社会学を専門とする社会学者。都市社会生活における基本構造や変化を、平凡な事実の積み上げによって実証する「正常人口の正常生活」を唱えた。

最後に、お二人へ5年先の「未来の住まいの新定番」について伺ってみたところ、そこには多様な「ホーム」のあり方を提示し、誰もが主体的に選び取れる社会を目指す姿勢がありました。
「20世紀は住まいの特定の理想像が明確に示され、それに向けて国民が動員されていく時代でした。それは非常にパワフルな時代でもあったと思います。しかしこれからの住まいは、ひとつの定番やスタンダードには集約されない、もっと多様なものになると思います。家が軽い人から、重いままの人まで、そのグラデーションのなかで、類型的になっていくのではないでしょうか」(平山さん)
「平山先生のおっしゃるグラデーションのなかで、一人ひとりが自分にとっての“ホーム”との距離感や、どこに帰りたいかといった帰属先への意識に合わせて自由に選び取れる、豊かな選択肢が提示される社会になると良いですね」(石神さん)
最後に、今回の議論の入り口となった「ホームフル」について、石神さんはこのように続けました。
「わたしたちと“ホーム”や“家”との関係性は、時代に応じて変化しつつ、同じ円の上をぐるぐる回っているようにも思えます。“ホームフル”の感覚も都市に住む感覚もほとんど同じかもしれませんが、同時にそれは変奏でもあって、テクノロジーやシステムなど、何が原因となってその変奏が引き起こされているのか、これからも考えていきたいと思います」(石神さん)
編集後記
アドレスホッパーという言葉をよく聞く時期がありました。そういえばあの人たちは今どうしているのだろう。その答えが、5年先の未来の住まいの考え方のヒントになるのでは?と取材させていただきました。取材を通して感じたのは、これからの住まいはモデルケース的なものはなく、人それぞれのスタイルがあり、それを分かち合う。認知とつながりで形成されるような印象をうけました。そして、住まいは物質的に形成されるというよりか、人々の心理的なもの表れのように感じました。
(未来定番研究所 窪)
地元の見る目を変えた47人。
二十四節気新・定番。
二十四節気新・定番。
地元の見る目を変えた47人。
地元の見る目を変えた47人。
未来工芸調査隊
未来命名会議<全9回>
未来の住まい定番を発見!5年先のインテリアカタログ。<全3回>
地元の見る目を変えた47人。
二十四節気新・定番。
二十四節気新・定番。
地元の見る目を変えた47人。
地元の見る目を変えた47人。
未来工芸調査隊
未来命名会議<全9回>
未来の住まい定番を発見!5年先のインテリアカタログ。<全3回>
未来の住まい定番を発見!5年先のインテリアカタログ。<全3回>
未来の住まい定番を発見!5年先のインテリアカタログ。<全3回>
あの人が選ぶ、未来のキーパーソン。<全4回>
わたしの「しない贅沢」。<全4回>
F.I.N.的新語辞典
わたしの「しない贅沢」。<全4回>
F.I.N.的新語辞典
F.I.N.的新語辞典
F.I.N.的新語辞典
F.I.N.的新語辞典
目利きたちに聞いた、これからの暮らしのマイルール。<全2回>
目利きたちに聞いた、これからの暮らしのマイルール。<全2回>
F.I.N.的新語辞典
F.I.N.的新語辞典
F.I.N.的新語辞典
F.I.N.的新語辞典