

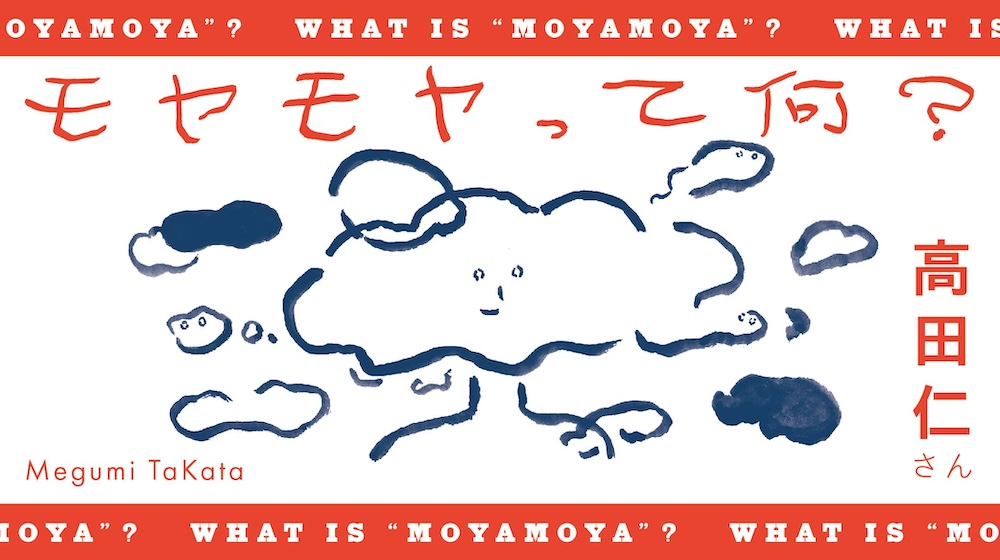
最近のF.I.N.編集部が大切にしている、考えを熟成するための「モヤモヤ」する時間。「モヤモヤ」と一口に言っても、日常でふと感じる違和感だったり、課題が整理できていない状態だったり、自分や誰かのモヤモヤであったりと、その種類はさまざまです。ポジティブに捉える人もいれば、そうでない人もいるかもしれません。この特集では「モヤモヤって何?」という問いを出発点に、時代の目利きたちと5年先の未来を探っていきます。
今回ご登場いただくのは、世界で活躍する起業家や経営者を輩出している九州大学大学院の教授・高田仁先生。数年前から、すぐに答えを出さなくてもいいという「モヤモヤする力」を日常に取り入れているといいます。なぜ、高田先生はモヤモヤする力を信じるのでしょうか。「モヤモヤ」と一緒に生きることで起きた変化とは? 高田先生の言葉から探ります。
(文:船橋麻貴/イラスト:紺野達也/サムネイルデザイン:佐藤豊)

高田仁さん(たかた・めぐみ)
九州大学大学院経済学研究院産業マネジメント専攻(九州大学ビジネス・スクール)教授。専門領域は技術商業化とアントレプレナーシップ。大手メーカー、コンサルタント、技術移転機関の取締役を経て現職。九州大学のアントレプレナーシップ・センターも兼務。企業の新規事業開発やVC投資委員会のアドバイザーなどにも尽力している。
モヤモヤと悩み続けることで、
自分なりの正解を見つける
僕が本格的にモヤモヤする力を取り入れ始めたのは、コロナ禍に入った頃。それまではとにかくもう仕事人間で、休みの日も仕事のことばかり考えていました。大学の教員になるまでは何度か転職をしていて、その度に「自分がやりたくないことはやらない」と思うものの、いざ働くと目の前のいろいろなことが気になって無理をしてしまう。
それは20年ほど前に大学の教員になってからも同じ。朝から晩まで死に物狂いで働いて、自分の生活はつい後回し。心身ともに疲弊する毎日でしたが、海外出張でその土地の文化やそこで暮らす人たちの考えに触れるうちに、プライベートを含めて自分らしい価値観をしっかりと持って生きていきたいと思うようになりました。むしろ、そうしないと精神的に押しつぶされてしまう。そんなところまで追い詰められていました。
それで10年くらい前から、朝にウォーキングや瞑想をしたり、マインドフルネスを取り入れたりもしたのですが、モヤモヤにきちんと向き合うきっかけはコロナ禍の訪れ。皆さんそうだと思いますが、緊急事態宣言が出されると出口の見えない不安でいっぱいになりました。この先どうなっちゃうんだろう、どう生きていけばいいんだろうと。そんな時に出会ったのが、すぐに答えを出さずにじっと待つ「ネガティブ・ケイパビリティ」の考え方でした。
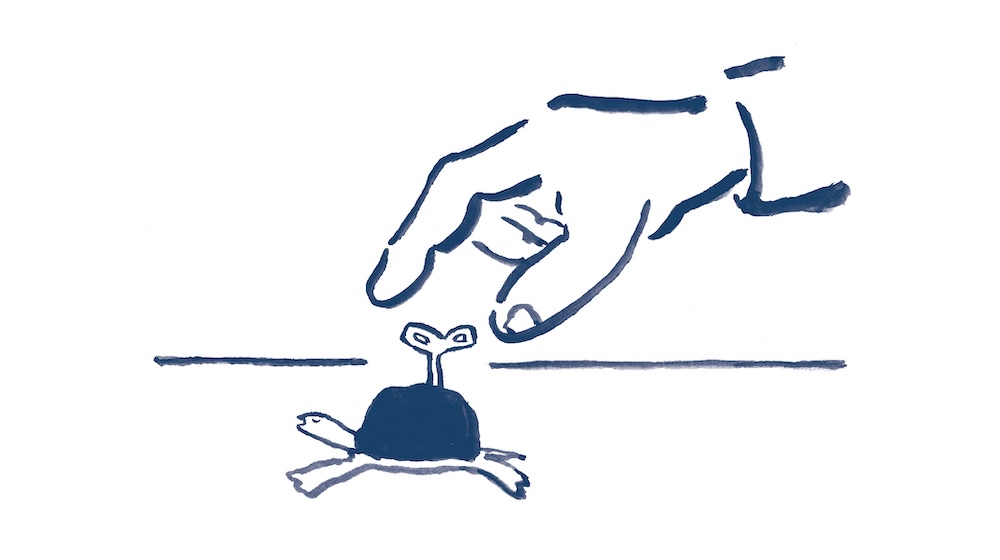
こんな考え方があるなんて……。できる限り早く答えを出すことを良しとしてきた僕にとってはあまりにも衝撃的だったので、提唱されている精神科医の帚木蓬生(ははきぎ・ほうせい)先生にすぐに会いに行ったのです。帚木先生とお話しするうちに、自分が教員として抱えているモヤモヤの捉え方が変わっていくような気がしました。
普段、僕は大学院で新規事業の創造や起業家としてのあり方などを学生たちに伝えているのですが、学生たちに新規事業について考えてもらうと、どこかで聞いたことのあるアイデアが出てくることが多くて。それこそ、SNSに転がっているようなアイデアだったり……。
そういう教員としてのモヤモヤが少なからずあったのですが、ネガティブ・ケイパビリティの観点から考えてみると、これは学生個人の問題ではなく、誰もやったことのない事業や価値を生み出すには、じっくりと問題や課題に向き合う時間や機会が足りないのではないかと。答えがなかなか出ないもの、正解がないものに対してモヤモヤと悩み、考えるのに時間がかかったりするのは当たり前。だって前例がないことに挑戦しているのだから。だからこそ粘り強く考え続けて自分なりの正解を導き出す。そういうモヤモヤに対する捉え直しが、学生にとっても自分にとっても必要なのだと感じました。
もちろん、周りの状況をわかろうとしたり、意味付けしたりするのは、生物である以上は必要なこと。ただ、わかろうとして答えを急ぐあまり、インスタントに得られる答えで代用してしまっては、想定外の事態が起きた時に対処できなくなってしまう。今僕たちが大切にすべきは、答えが出ないという宙ぶらりんの状態でありながらも、冷静に丁寧に向き合い続けること。そう思いました。
高田先生が実践する
モヤモヤする力の取り入れ方
モヤモヤする力を大切にしたいと思った僕は、早速この考えを生活に取り入れ始めました。その具体的なアクションは主にこの3つ。
①すぐに答えを出すことをやめる。
今、AIの台頭によって理想的な答えにすぐにたどり着けるようになりましたが、それは人が持つ好奇心を奪うことになりかねません。だから、僕たちが考え続けるためにも、不確実性の中に身を置くことが大切。すぐに白黒つけずにずっと問い続けることは苦しいし、答えを出せない自分にモヤモヤするかもしれません。だけど、答えがすぐに出るのだったらどこかの誰かがさっさと実現しているはずなので、むしろそれくらい新しいことに挑戦している自分を誇りに思っていい。答えの出ない事柄に対して「今はわかりません」と言っていいし、反対にそんな難しい問題や課題に対して、わかったふりをして答えを急がない方がいいと思っています。
②答えの出ないことは、周りを巻き込んで実験的に挑戦してみる。
すぐに答えを出すことはやめましたが、答えを出すこと自体を諦めるわけではありません。僕が大学院でよくやるのは、時間をかけて実験的にトライすること。その時は自分1人で抱え込まずに、周囲の仲間の力を借りて、一緒に問いと向き合うようにしています。それでも答えが出なかったり、失敗したりすることは当然あります。だけど答えが簡単に出ないのは当たり前ですし、そこで起きた失敗は失敗ではありません。「当初想定していなかった新しい事実を発見できた」と捉えるようにしています。
③「モヤモヤする時間」と「問題を解決する時間」を意識的に使い分ける。
忙しい毎日の中で僕が大切にしているのは、「モヤモヤする時間」と「問題を解決する時間」を午前と午後に分けること。もちろんきっちりと分けられるとは限りませんが、できるだけこの2つは切り離すようにしています。例えば、頭と心に余白がある午前中は「モヤモヤする時間」として、新しい研究や教育プログラムの構想をしたりと、すぐに答えが出そうにないことを考える時間にあてています。一方、午後は「問題を解決する時間」。会議やメールする時間にあて、すぐに処理ができることや結論が出ることを重点的に行っています。
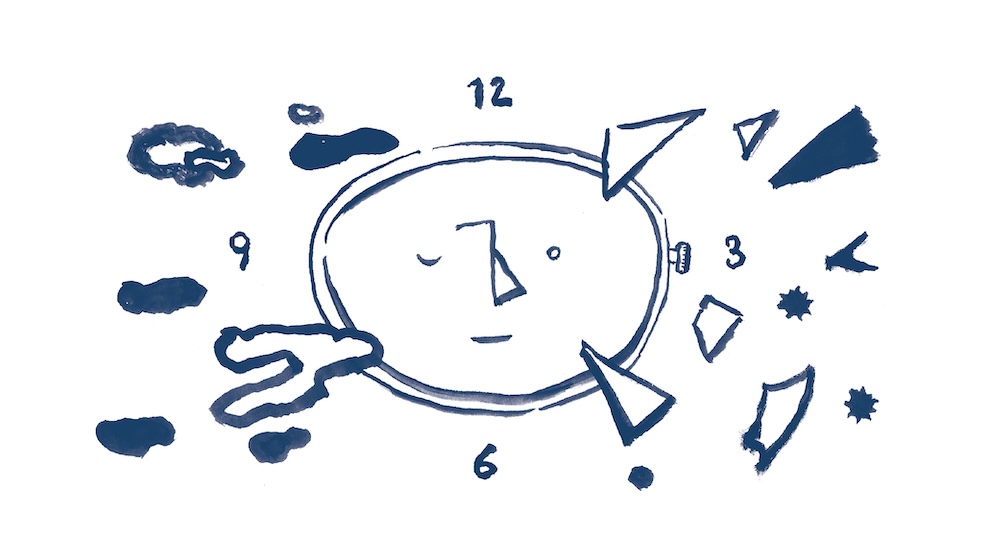
自分の価値観を見つめ直し、
余白のある日常を守っていく
こうして意識的にモヤモヤに対して無理に答えを出さなくなってから、4年ほど。自分の中での大きな変化は、日常の豊かさに気づけたこと。答えを出さないといけないストレスとプレッシャーから解放され、じっくりと問いと向き合い続けられることで、新たなアイデアが生まれることも増えたような気がします。
そして今、「モヤモヤって何?」という問いに対して僕は、「すぐにわかった気にならず、気長に向き合い続けること」と答えます。そのために、自分の頭と心には「余白」を持っておく必要がある。自分の中に余白があれば、遊びをきかせられますから。これは仕事だけでなく、日常においてもとても大事だと思っています。
例えば僕の場合だと、早めに仕事を終えて家に帰った日は、近所の海沿いの公園で妻と愛犬と一緒に散歩しながら、夕陽を見ながらぼんやりと過ごすことが今の幸せ。そこに冷えたビールか、白ワインがあったら最高なのですが、こうしたことはやっぱり自分の中に余白がないとできません。
日常の豊かさに気づけた今、この先最も大切にしていきたいのは、モヤモヤと向き合って作った余白を簡単に他者に受け渡さないこと。せっかく余白や遊びを人生に取り戻せたのだから、大切に守っていきたい。そういう意味では、モヤモヤすることは悪いことじゃないかもしれませんね。なぜなら、働くこと、そして生きることの価値観を見直すきっかけになったのですから。

【編集後記】
「ものごとはまず思い通りに進まない」「やったことがないことはわからなくて当たり前」。数々の勇気が湧く言葉とお話ばかりで、それは少しの量ですごくきれいになる洗剤のように心のゴリゴリがとれていくようで、伺いながらうれしい気持ちがぐるぐる体内を走り回っていました。
どうしても「ちゃんとやんなきゃプレッシャー」を自分に暗示してしまいがちなのですが、呪文のようにネガティブ・ケイパビリティを唱えてさっそくフル活用する日々です。
自分の大切な時間をかんたんに他人に奪い取られないようさりげなく防御しつつ、クオリティータイムと克己心をしっかり保ち、日々過ごしたいと思います。
(未来定番研究所 内野)

帰り道 谷中のクオリティータイム