二十四節気新・定番。


2022.03.16
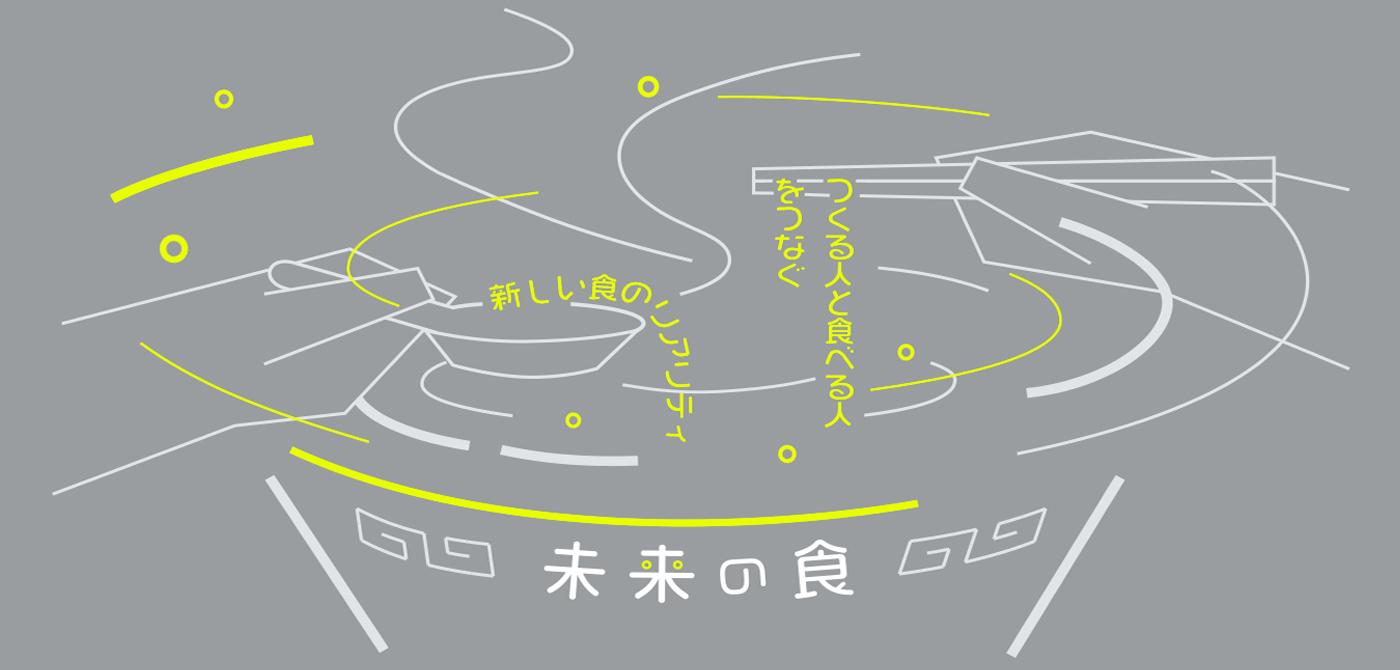
2018年4月開設の立命館大学「食マネジメント学部」では、「食」に関する深い知見と社会での実践力を養う、多角的な学びを展開しています。
前篇では、食マネジメント学部で教鞭をとる先生方5名に「未来の食のキーワード」を教えていただきました。中でもF.I.N.編集部が注目したのは、吉積巳貴先生の生産者と消費者の関係性を切り口にした【つくる人と食べる人をつなぐ】、石田雅芳先生の、変化する食の教育現場を切り口にした【新しい食のリアリティ】の2つのキーワードです。後篇では、2つのキーワードを深掘りすべく、F.I.N.編集部からの質問をぶつけてみました。
(文:池尾 優)
キーワード【つくる人と食べる人をつなぐ】
作り手が遠くなるほど、環境への負荷も増える?
F.I.N.編集部
吉積先生は前回のインタビューで、【つくる人と食べる人をつなぐ】を挙げながら、現代の大きな問題として生産者と消費者の間に距離が生まれていることを指摘されました。どういったことが問題なのか、詳しく聞かせていただけますか?
吉積先生
前提として、全ての食は自然環境があって成り立つものです。食の生産や流通のグローバル化が拡大する今は、身近で作られた食べ物よりも、効率性や価格の安さなどから他地域や他国から輸入したものが選ばれがちです。すると、当然その産地では土地の資源が使われますし、それが生産者の居住環境への負荷にもつながります。生産時に温室効果ガスが排出されますし、運ぶ際にも大きなエネルギーが消費されます。生産や運搬の過程で多方面に影響を与えているのです。にもかかわらず、食の生産流通システムが拡大することで、我々消費者にはその影響が見えづらくなっています。ここが大きな問題なんです。

食品の生産・運搬の過程が環境問題に影響を及ぼしていることは、前篇の記事で【環境にも健康にもやさしい食】をキーワードにあげてくださった天野耕二教授もおっしゃっていました。(写真:YUTAKA/アフロ)
F.I.N.編集部
世界中のものがいとも簡単に手元に届きます。その手軽さから、ものの背景をイメージするのが難しくなっているんですね。
吉積先生
そうなんです。逆に、もし身近な場所で作られたものを選べば、生産や運搬の過程で起こるあらゆる問題に、消費者が気づきやすくなる。例えば大学のキャンパスのある滋賀県では、気候変動から自然災害が起こりやすくなっていると言われており、農作物の収量が安定しなかったり、琵琶湖では漁師さんの漁獲量が減ったりもしています。ですが、現在の流通システムでは滋賀県産の食材は大阪や京都に流れており、滋賀県内の消費者にしてもスーパーやネットで県外産の食材を買うような状況になっています。そこで必要になるのが、やはり生産者と消費者をうまく繋げる仕組みです。
つながるきっかけは、ゼロウェイスト。
生産者と消費者がつくる、食の未来。
F.I.N.編集部
それを既に実践しているのが、先生が前編で挙げてくださった、生産者と消費者を直接つなぐスマホアプリ〈ポケットマルシェ〉ですね。他にも同様の事例はありますか?
吉積先生
生産者と消費者がリアルな場で交流するファーマーズマーケットはその先駆けですが、現在はオンラインの事例も多くみられるようになってきています。自社のECサイトやアプリで小さな規模でされるところもあれば、クックパッドの〈クックパッドマート〉のように大きなプラットフォームもあります。京都では近年、ゼロ・ウェイスト(廃棄をゼロにする)を目指すスーパーマーケット〈斗々屋〉ができました。量り売りで販売することでプラスチックゴミを出さず、店内のレストランでは食品ロス対策として賞味期限が近づいている生鮮食品を使ったメニューを提供しています。さらに調理の際に出たゴミはコンポスト化して契約農家さんの元へ持って行く。ゼロウェイストを通じて、小売店が拠点になりながら生産者と消費者をつなぐ循環ができています。

2021年7月、京都市上京区にオープンした、日本初のゼロ・ウェイスト・スーパー〈斗々屋(ととや)〉。包装材などのごみを出さずに、容器を持ち込み、量り売りですべての食品や日用品を購入できる。
F.I.N.編集部
私たちも、コンポストを通じたコミュニティ醸成に注目しています。百貨店としてどんなことができるか試行錯誤していますが、例えば自治体さんと連携して都会の真ん中でコンポストを通じて消費者と生産者がつながる。そんなコミュニティ醸成ができたらとは思うのですが、どう運営していくかのところがなかなか難しくて。
吉積先生
そうですね。こうした取り組みは各地で増えており、技術と仕組みはあるものの、経営的にどう回していくかが大きな壁です。例えばフードロスの観点でも、国や世界レベルで「食品全体の3分の1が廃棄されている」という話は認識されつつあり「フードバンク」など、食べられるものを必要な人に届ける様々な仕組みができています。ですが、ボランティアベースや補助金頼りになっているケースも多いです。ビジネスとして持続的に運営していく仕組みづくりが課題になっていますね。
F.I.N.編集部
継続していくのには、仕組みに加えて個人のモチベーションも大事に思います。なにごとにも“楽しくないと続けられない”ということもあるかと思います。
吉積先生
エネルギーや環境問題は身近に感じにくいトピックスです。そのなかでも、食というのは自分事にしやすいテーマなので、入り口として最適なように思います。自分の食べるものが美味しくあるためには、自然が豊かでないといけない、ということですから。嬉しいことに、食マネジメント学部では農業を志望する学生が増えているんです。実際、1学年約300人のうち3割が農業に携わることを希望していて、さらにその多くが実家が農家などではなく、これまで農業に関わってこなかった子たちなんです。
F.I.N.編集部
それは、食の未来にとって大きな希望ですね。食の観点から地域を考えられる学生が大人になったら、先生の考える“食べる人と作る人をつなぐ”社会も近づくように思います。

吉積巳貴
立命館大学 食マネジメント学部 食マネジメント学科 教授
専門は環境まちづくり、環境教育、持続可能な発展のための教育(ESD)など。地球環境学博士。国連地域開発センター防災計画兵庫事務所リサーチアシスタント、京都大学大学院地球環境学堂助教、京都大学学際融合教育研究推進センター森里海連環学教育ユニット特定准教授、立命館大学食マネジメント学部准教授を経て、2019年4月より立命館大学食マネジメント学部教授。近年の共著に『SDGs時代の食・環境問題入門』(昭和堂)。
キーワード【新しい食のリアリティ】
変化する食の教育現場。本物を見ることの意味とは?
F.I.N.編集部
石田先生は前回のインタビューで、【新しい食のリアリティ】をキーワードに挙げながら、リモート教育の可能性を感じていらっしゃると教えてくださいました。先生はイタリアの食が専門なので、現地実習ができないのは大きな障壁でありながら、そんな状況だからこそ新たな学びの手法が生まれたように感じます。
石田教授
ここ2年間で、新しい食のリアリティを追求する学びの手法が醸成されたと思います。なかでも、日伊の食文化を出合わせガストロ・エデュ(Gastronomic Sciences Educationの略=食文化教育)は大きな広がりを見せています。日伊の同じ食材をフックにそれぞれの生産者をオンラインでつないで交流をはかり、それを誰でも参加できるオンラインイベントとして生配信するインタラクティブな企画です。前篇でお話しした北イタリアのピエモンテ牛と岩手県・岩泉町の短角牛の会を含め、トマトやレモンなどこれまでに計7回開催しました。

立命館大学が附属中学校4校と連携し行ったガストロ・エデュの様子。この日は、レモンを題材に「柑橘類の生物多様性」を考えるため、バレンシアのレモン農園とライブ中継で繋いだ。(実習のレポートはこちら)
F.I.N.編集部
牛をテーマにした際には、オンライン配信に加えて仙台のテレビ局でも放映されたと伺いました。学生はこうした配信や放映を観て学ぶ、ということなのでしょうか?
石田教授
いいえ、学生はプロジェクト運営側で主体として関わっています。それを学外へ発信する活動になります。たとえば2020年8月に3日間に渡り開催した『Tomato Adventure』では、立命館大学附属の小学校高学年を対象にオンラインワークショップを開催しました。全員がリモート参加で、「真のナポリピッツア協会」の会長やイタリアのトマトの生産者さんも招いて行いました。
F.I.N.編集部
小学生たちも、イタリアの現地の方たちからお話を聞けたということですね。一昔前の社会科見学では体験できない、インターネット全盛時代ならではの食育ですね。
石田教授
そうですね。オンラインを介して、小学生たちがトマトを題材に食品ロス問題について考えたり、食品ロスを解決するオリジナルトマト料理を考え提案したり、ナポリのピザ職人に教えてもらいながらピザを作ったりと、参加型のワークショップでした。
F.I.N.編集部
食は多面的に考えることができるテーマとして、こうした企画との相性も良さそうです。
石田教授
そうなんです。食の学びというのは、隅から隅まで覚えて段階を追って、というものではなく、非常に複雑なものに向かっていかなければなりませんので。
ちなみにこの取り組みは、運営側の学生にも大きな学びがあります。ガストロ・エデュは文科省が支援する次世代アントレプレナー育成事業「EDGE―NEXT」との連携で行なっている企画でして、学内での学びを基にした起業や新事業創出に挑戦する人材の育成や関係機関によるベンチャー・エコシステムの構築を目的としています。学内での学びが、将来のビジネスや起業に繋がるような場になればと思います。共同で行なっているのが同じ学部准教授の野中朋美先生で、彼女はアメリカで毎年開催される世界最大級の複合イベント「SXSW」でも持続可能な食をテーマにしたイベントを共催するなど、海外への発信も積極的に行う研究者です。

立命館大学EDGE+Rプログラム副総括責任者でもある野中朋美先生(右)は、鎌谷かおる先生(左)と共同で〈EdoMirai Food System Design Lab〉を立ち上げ、SXSW 2019で「The Kitchen Hackerʻs Guide to the Food Galaxy in SXSW」を共催。江戸から学ぶサステイナビリティ「Edo Sustainability:もったいないからちょうどいい」を世界に向けて発信した。
F.I.N.編集部
食を取り巻く市場は多岐に渡るので、その意味でも、オンラインを上手く活用したガストロ・エデュの学びは学生の将来、様々な形で生きてきそうです。
石田教授
フットワークの悪くなった教学環境において、学生に現場を見せたい、という思いから始まりました。また、海外旅行に行く人が減っているなど若い世代の国際性が乏しくなっている今、学内だけでなく広い世界を見てほしいという思いもあります。
F.I.N.編集部
ガストロ・エデュと並行して、衛星回線を使った計画も進行中と伺いました。
石田教授
同じく野中先生と一緒に3年間構想で進めているのが、人工衛星回線を使った衛星インターネットアクセスサービスの導入です。リモート教育でも本格的に“外に出て”しまう、ことを狙っていて。というのも、これまでのように電話回線とWIFIではネット回線のあるエリアに限定されるので、食のリアリティはほとんど見られないんです。ブドウ畑にも行けなければ、漁船にも乗れません。衛星回線なら僻地と言われる場所を含め、世界の隅々まで手が届く。これを導入することで学部全体の学びのプラットフォームができあがるのはもちろん、学部全体の食の世界ネットワークも構築していきたいと思います。
F.I.N.編集部
まさに、食のリアリティを、世界の隅から隅まで追求できそうです。実現すれば、様々な先生の講座やゼミで人工衛星を使った学びが享受できるようになるんですね。吉積先生の話にもあったように、食の理解はやはり現場を見ることで深まる部分が大きいと思います。このプラットフォームで学びとネットワークの双方が無限大に広がっていきそうです。

石田雅芳
イタリアの食文化、スローフード哲学と食のアクティヴィズム専門。スローフード協会イタリア本部の唯一の日本人スタッフとして、スローフード・ジャパンの創立を始め、食の国際ネットワークにアジア初として日本の参加を促進。2018年4月より立命館大学食マネジメント学部教授。同志社大学大学院文学研究科修士課程修了。共著に『スローフードマニフェスト』(木楽舎)、『食と農のコミュニティ』(創元社)、訳著に『スローフードの奇跡』(三修社)。
【編集後記】
生活者にとって馴染み深い”食”というテーマ。
”食”のあらゆる問題へのアプローチ方法は、問題の構造が複雑だからこそ、多種多様なアプローチが出来るのだなと勉強させていただきました。
生産者と消費者がつながる事の目的は、”食”の問題を自分ごと化し環境問題を考える意識を醸成する事だと改めて実感いたしました。
(未来定番研究所 小林)
二十四節気新・定番。
5年後の答え合わせ
5年後の答え合わせ
F.I.N.的新語辞典
F.I.N.的新語辞典
F.I.N.的新語辞典
F.I.N.的新語辞典
二十四節気新・定番。
5年後の答え合わせ
5年後の答え合わせ
F.I.N.的新語辞典
F.I.N.的新語辞典
F.I.N.的新語辞典
F.I.N.的新語辞典
未来を仕掛ける日本全国の47人。
未来を仕掛ける日本全国の47人。
人工知能が切り拓く、食卓の未来。<全2回>
わたしのつくり方
わたしのつくり方