未来工芸調査隊


1人目
2人目
3人目
4人目
5人目
6人目
7人目
8人目
9人目
10人目
11人目
12人目
13人目
14人目
15人目
16人目
17人目
18人目
19人目
20人目
21人目
22人目
23人目
24人目
25人目
26人目
27人目
28人目
29 人目
30人目
31人目
32人目
33人目
34人目
35人目
36人目
37人目
38人目
39人目
40人目
41人目
42人目
43人目
44人目
45人目
46人目
47人目
2018.10.29
未来を仕掛ける日本全国の47人。
毎週、F.I.N.編集部が1都道府県ずつ巡って、未来は世の中の定番になるかもしれない“もの”や“こと”、そしてそれを仕掛ける“人”を見つけていきます。今回向かったのは、京都府の京都市。編集者の軍地彩弓さんが教えてくれた、レストランプロデューサーの宮下拓己さんをご紹介します。
この連載企画にご登場いただく47名は、F.I.N.編集部が信頼する、各地にネットワークを持つ方々にご推薦いただき、選出しています。
京都から世界へ。”日本ならでは”の新たな食カルチャーを発信する人。
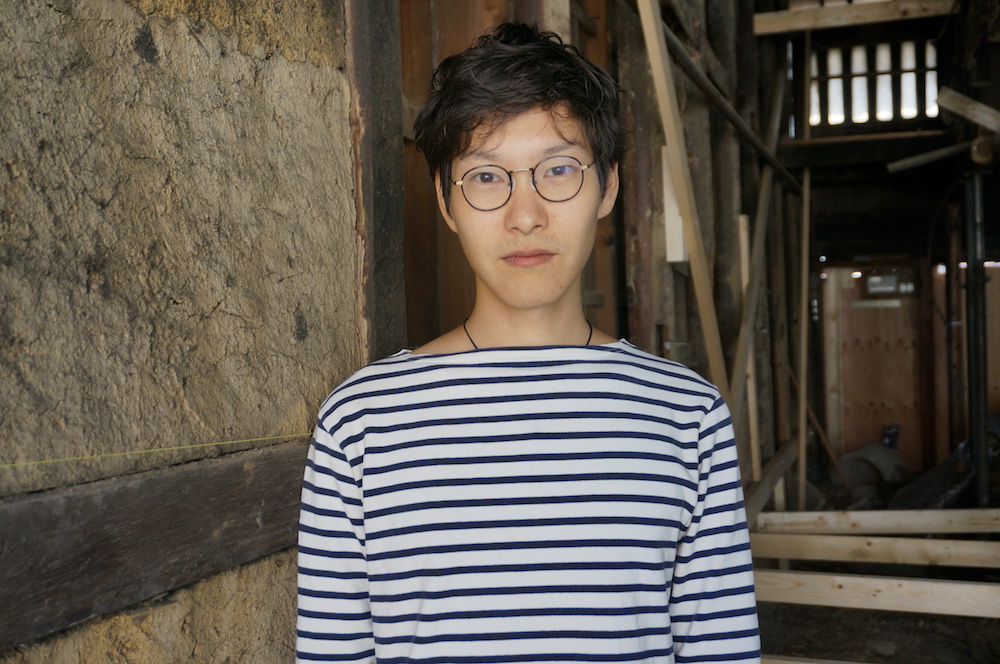
東京や大阪、さらにはオーストラリア・メルボルンや、ニュージーランド・オークランドなど、世界の数多の都市の有名レストランを渡り歩き、サービスの立場から食のストーリーや背景を伝える活動を続けてきた宮下さん。「とにかく人が好き」と話す彼が次に挑戦をする都市は、京都。東山地区三条駅近くの町屋をリノベーションし、新しいレストラン〈LURRA˚〉を立ち上げるべく、準備を進めています。推薦してくださった軍地さんは、「彼らは、京都・大原の食材を使って、伝統を踏まえながらも革新的な料理を作ろうとしています。伝統が息づく京都という街を舞台に、どこにも属さずインディペデントで勝負していて、新しい食カルチャーを世界に発信しようとしている。まだまだ20代ながら、世界中を渡り歩いて友人を作り、全く縁がない京都に根を張って、未来を作ろうとしている姿が素晴らしいと思っています」と話してくれました。宮下さんにお話を伺ってみました。
F.I.N.編集部
本日はよろしくお願いします! そもそも宮下さんが、食に関わるお仕事をしたいと思ったのは、どんなきっかけだったんですか?
宮下さん
昔から、みんなに「自由」と言われる子供で、学校の勉強よりも読書が好きでした。「好きなことをやれ」と家族もずっと背中を押してくれていたので、高校を卒業した後は、進学ではなく、漠然と、もともと好きだったアートの方面に進みたいなと思っていましたね。
F.I.N.編集部
なるほど。最初から食に関係する仕事を思い描いていたわけではなかったとは、意外です。
宮下さん
そうなんです。ただ、絵が描ける訳ではないので、何か好きなものを探そうと、いろんな本を「ジャケ買い」して読みふけっていきました。その時に、世界の食のトレンドを特集した雑誌をたまたま手に取り、スペインのエルブジというレストランの記事を読んだんです。エルブジは、食べるという行為の“体験”をうまく表現していたレストランで、食は、唯一五感が使えるアートだなと感じたのを覚えています。それをきっかけに、食に関わる仕事がしたいと思うようになり、高校を卒業して、辻調理師専門学校、そして上級校のフランス校に通いました。
F.I.N.編集部
食もアートのひとつだと気付かれたんですね。
宮下さん
学校を首席で卒業できた僕は、現地の三つ星レストランMichel Brasで研修をする機会をもらえました。研修先のレストランは、半径50キロくらいは駅もないような山奥にありました。研修中、その土地で生まれ育ったシェフがある日急に、「今日の空は綺麗だね」と僕に話しかけました。僕からすると、その土地の空は毎日同じように綺麗に見える。でも彼は、60年間毎日眺めているはずなのに、その美しさの日々の違いを感じ取っていたんです。僕にとっては衝撃的でした。シェフというのは、料理技術以前に、自らの感性に基づいて表現する仕事なんだなと感じたことを覚えています。

研修先のフランス・ブルゴーニュにて。
F.I.N.編集部
なるほど。
宮下さん
研修を終えた後は、大阪の三つ星レストランで働きました。最初は料理がしたいと思っていたのですが、サービスの担当から経験させるというお店だったので、接客に従事しました。接客をする中で感じたのが、料理はどんなにすごく素晴らしくても、それを伝えるものがないと活きないということ。もともと人が好きだということも重なり、それを機に、食のストーリーや背景をちゃんと人に伝える仕事がしたいと思い始めました。
F.I.N.編集部
そこで”作る”ことから、”伝える”ことに意識が向かれたということでしょうか。
宮下さん
はい。その後は、東京のレストランに移り、ソムリエの仕事を学びました。お酒が持つ、人を笑顔にする力やお客さんをつなぐ力ってすごく強いと思うんです。ワインを知っていることで、自分の伝える言葉の説得力もつくので、ソムリエの資格を取りました。そのお店では2年間くらい働いたのですが、ある時ふと気づいたんです。あっ僕、英語できないなと(笑)。
F.I.N.編集部
そうなんですか! フランスにもいらっしゃったのに?
宮下さん
拙いフランス語と、あとは笑顔と気合で乗り切ってきたので……(笑)。でも、英語を話すことができたら、もっと多くのことを多くの人に伝えられるのではないかと。そこで思い立ち、オーストラリア行きを決心しました。
F.I.N.編集部
オーストラリアでは、英語の語学学校に通われたんですか?
宮下さん
普通はそう思いますよね。でも、行ってみたらなんとかなるだろうと思って、一番コースの値段が高く、ワインリストが一番多いレストランに、いきなり履歴書を送ったんですよ(笑)。
F.I.N.編集部
凄まじい行動力ですね……。
宮下さん
冷静に考えれば、訳わからないですよね(笑)。ただ、僕の人生訓のひとつにあるのが、山に登る時は、一番高いところにものを投げてみて、引っかかったところをよじ登ってみようということ。とりあえず行けるだけ上を目指してみようと思っているんです。もちろん、堅実に積み上げることの大事さというのもあると思いますが、僕はあとから足りないものを補っていこうと考えているんです。
F.I.N.編集部
宮下さんのチャレンジングさも、その人生訓から来ているんですね。お店の反応はいかがでしたか?
宮下さん
とにかくレストランが好きで、お客さんが好きで……、と思いをぶつけた結果、研修させてもらえることになったんです。でも、当然最初は、簡単にはお客さんとも話せない。それでも笑顔で明るく働いていたら、シェフソムリエが「お前なら大丈夫だ」と見込んでくれました。それからは、彼が毎日2時間早く出勤してくれて、僕に英語とワインを教えてくれたんです。彼は、一昨年のベストオーストラリアソムリエに輝いた人で、向こうからしたら何の得もないはずなのに……。そこでしっかりワインと英語を学べたことが、何よりもの経験になりました。
F.I.N.編集部
宮下さんのお人柄故に、シェフソムリエの心も掴まれたのだと思います。
宮下さん
さらに、そのお店では、素晴らしいマネージャーにも出会いました。普通、レストランという環境は、忙しくなると殺気立ってくるんです。その時、マネージャーというのは中でも一番ピリピリしている存在。ですが彼は、わざとふざけたことを言ったり、煽ってみたり。ポジティブに人を鼓舞するタイプでした。お客さんのことを一番に考えると、スタッフたちが働きやすい状況を作ることが大切なことは、みんな頭ではわかっているけど、なかなかで出来ない。そのマネージャーの姿を見て、これは本当に人が好きな人の働き方だなと感じ、素直にかっこいいなと思ったんです。シェフソムリエと、このマネージャーに出会えたことが、僕の人生では転機となりました。

オーストラリアのレストランで働く宮下さん。
F.I.N.編集部
本当に素敵な出会いですね。その後はいかがされたんですか?
宮下さん
その後は、ニュージーランドに行きました。そこでは、今〈LURRA˚〉の立ち上げを一緒に進めているJacob Kearというシェフに出会います。彼はもともと世界NO.1レストランとして有名な、デンマークのノーマ〈Noma〉で働いていました。彼は、日本とアメリカのハーフで、日本人の感覚を持ちつつも海外的な要素も持ち合わせるシェフで、以前から注目していました。当時、彼がニュージーランドにいることも知っていたので、次はこの人と働きたいなと思っていました。
F.I.N.編集部
ということは、Jacobさんをめがけてニュージーランドに行ったんですか?
宮下さん
そうなんです。知り合いのシェフが仲介してくれて、僕はソムリエ部門のトップとして、彼と同じお店で働くことができました。さらには、そのお店のバーテンダーのトップも日本人だったんです。偶然に日本のバックグラウンドを持った3人が集まって、ニュージーランドのミシュランとも言われる雑誌で、”3ハット”という一番上の格を取れたことをきっかけに、日本に拠点を移し、3人でお店をやってみようということになりました。

左から、宮下さん、シェフのJacob Kearさん、ミクソロジスト(バーテンダー)の堺部雄介さん。
F.I.N.編集部
そこから、〈LURRA˚〉の立ち上げが進むんですね。なぜお店を出す場所として、京都を選ばれたんでしょうか?
宮下さん
大きな理由としては、伝統と革新、自然の3つが、バランス良く共存している街であることです。伝統と革新の2つを持ち合わせた街は、京都以外にも、パリやミラノなど、実はたくさんあるんです。でも、伝統と革新の中に、自然が入ってくる都市って実はあんまりない。レストランはベースとして食材が大切。市内から車で20分ほど行けば、大原に畑が広がっていて、食材を自分たちで畑や山に入って取りに行ける環境があることに、惹かれました。

建築が進む〈LURRA˚〉。町屋をリノベーションして作られている。
F.I.N.編集部
確かに、それはなかなか共存しえない環境ですよね。
宮下さん
〈LURRA˚〉は、季節や文化のショーケースのようなお店にしたいなと思っています。日本には素晴らしい伝統があり、豊かな食材がある。海外のものをただ賞賛するのではなく、もっと日本に対してアプローチできることがあると思うんです。日本から日本の伝統、食材を発信し、体験してもらう場としては、京都という場が最適だなと考えました。
F.I.N.編集部
日本人にとっても響くところが多々ありそうです。
宮下さん
そうですね。対海外というだけではなく、自分たちが表現したいものをブレずに表現していけば、日本も含めた、世界中に響く場になるのではないかと思っています。僕は、〈LURRA˚〉を通して、ブームではなく、カルチャーを作りたい。ブームというのは、次の世代が登場した時に、ある意味”ダサい”と言われるものですよね。常に新しく居続け、世の中の流れに飲まれることなく信念を持ってやっていきたいと思っています。

京都・大原の豊かな畑。食材の産地へのアクセスのしやすさが、京都を選んだ理由のひとつなのだそう。
F.I.N.編集部
海外の多くのレストランで経験を積まれてきたからこそ感じる、日本の食のシーンに関しての課題はありますか?
宮下さん
もっとレストランにおいて接客を重視すべきだと感じています。接客はお客さんごとのオートクチュールであるべきだと思います。シェフというのは、料理を通じてお客さんを一気に感動させられる、インパクトがある仕事ですし、待遇も改善されてきているので、これからも増えていく。でも、接客は、お客さんに心地よいと感じてもらえることを積み重ねることが大切で、ある意味地道なもの。でも、これだけ世の中にたくさんのお店がある中で、食とお客さんの接点をどう取り持つか、その差は接客が担うと思っているんです。食のカルチャーを未来につないでいくためには、接客力をもっと伸ばすべきだと思いますし、働きやすさのサポートも徹底していかないといけないと思います。

〈LURRA˚〉ポップアップイベントの様子。

左は、シェフのJacob Kearさん。
F.I.N.編集部
待遇の面から変えていかなければいけないんですね。
宮下さん
そうですね。スタッフたちの満足度、は最終的にはお客さんの満足度につながっていくと思うので。例えば、〈LURRA˚〉では、サービス料のうちの数%を、スタッフに毎月還元しようと思っているんです。自分たちの頑張りが、しっかりとお金に変わることで、やりがいを感じてもらいたいんです。あとは、仕事柄、1日14時間くらいレストランにいることがあります。それが週5日間続くことを考えると、スタッフ一人ひとりが居心地良く働けることって大事だと思っているんです。日本の飲食は縦社会ですが、上下関係というのは、お客さんから見たらあまり関係のないもの。だから、〈LURRA˚〉では、そういう上下関係もなくしていきたいと思います。
F.I.N.編集部
提供する料理や時間というのは、スタッフの人たちが生き生きと働いてこそ楽しいものに変わっていきますよね。
宮下さん
それがお客さんにも伝わると思うんです。「おいしかった」というのはある意味当たり前。食事が終わった後は、まるで映画を1本見終わった後のように、「楽しかった」と思ってもらえる空間を作りたいなと。お客さんもレストランの一部なので、スタッフ、お客さん問わず、そこにいる全員で空気感を作り上げたいと思っています。
F.I.N.編集部
最後に、〈LURRA˚〉をどんな場にしていきたいとお考えですか?
宮下さん
レストランとしてだけでなく、スピンオフ的な活動を様々作っていける場にしたいと思っています。例えば、〈LURRA˚〉は、夜はレストランですが、昼はギャラリーとコーヒースタンド、夜はバーとして営業する予定です。レストランは、価格帯が高いですが、コーヒースタンドやバータイムがあることによって、いろんな人が来られる場になりますよね。僕は、人が好きなので、〈LURRA˚〉を通していろんな人に出会いたい。面白い人に出会うためには、こちらも間口を広げないといけないなと思っているんです。良い意味で、そこに生活感があるような、人々にとってのサードプレイスのような、それでいて、新しい活動が生まれる余白があるような、アメーバのような空間になれば良いなと思います。
F.I.N.編集部
オープンは来春予定とのことですが、今からオープンが待ち遠しいです! 本日はありがとうございました。
1人目
2人目
3人目
4人目
5人目
6人目
7人目
8人目
9人目
10人目
11人目
12人目
13人目
14人目
15人目
16人目
17人目
18人目
19人目
20人目
21人目
22人目
23人目
24人目
25人目
26人目
27人目
28人目
29 人目
30人目
31人目
32人目
33人目
34人目
35人目
36人目
37人目
38人目
39人目
40人目
41人目
42人目
43人目
44人目
45人目
46人目
47人目
二十四節気新・定番。
5年後の答え合わせ
5年後の答え合わせ
F.I.N.的新語辞典
F.I.N.的新語辞典
二十四節気新・定番。
5年後の答え合わせ
5年後の答え合わせ
F.I.N.的新語辞典
F.I.N.的新語辞典
人工知能が切り拓く、食卓の未来。<全2回>