

第1回|

さまざまな専門知を持つ目利きとともに、別の視点で百貨店を捉えてみる「百貨店の百視点」。これまで見過ごされがちだった百貨店の姿を探求すれば、新たな側面が見えてくるかもしれません。
第1回のテーマは、「街と百貨店」。地方百貨店への造詣が深い〈都市商業研究所〉の若杉優貴さんに、街のなかで百貨店が果たしてきた役割と、若杉さんが考える百貨店の可能性を伺います。
(文:船橋麻貴/イラスト:福澤遼)

若杉優貴さん(わかすぎ・ゆうき)
大分県別府市出身。熊本大学・広島大学大学院を経て、久留米大学大学院在籍時に街づくり・商業研究団体〈都市商業研究所〉に参画。大型店や商店街でのトレンドを中心に、台湾やアニメ、アイドルなど多様な分野での執筆を行いつつ、2021年に博士学位取得。専攻は商業地理学。趣味は地方百貨店と商店街めぐり。
地方百貨店は、街のインフラだった
一般的に、「買い物の場」や「街の顔」のイメージがある地方百貨店。しかし、若杉さんは、街の仕組み自体に寄与する存在だといいます。
「地方都市であればあるほど、百貨店1店舗の影響力は絶大です。百貨店がどこに店を構えるかで人の流れが変わり、中心市街地の姿が決まり、街の機能そのものが規定されてきました。百貨店は単なる買い物の場ではなく、都市構造に大きな影響を与える存在だと思います」
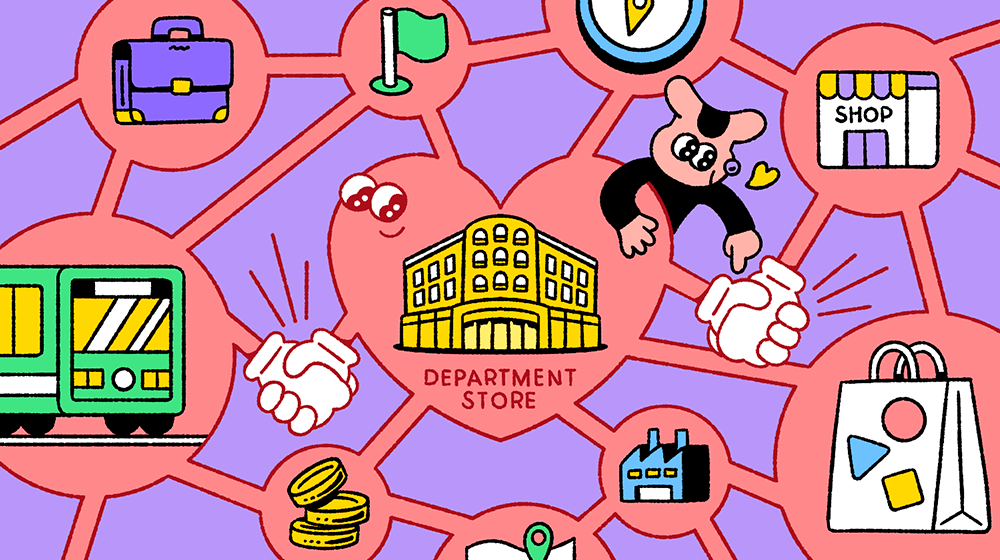
都市の仕組みそのものを左右するという百貨店。では、その機能がひとたび停止したとき、街に何が起きるのか。例えば秋田市では、かつて県内で最も集客力があった百貨店が長年休業状態にあり、活用されていないことが、街全体に大きな影を落としていると語ります。
「百貨店は、そこにあるだけで人の流れを生み出し、街を維持する心臓のような存在です。そのため、街の中心部にある大規模な建物と駐車場が稼働しなくなると、人々の意識は『隣の市のショッピングセンターに行こう』という外向きの流れへと傾き、街そのものの求心力が失われてしまいます」
ここで見えてくるのが、「動けない」という百貨店特有の宿命です。
「郊外型のショッピングセンターのように、時代の変化に合わせて最適な場所へ移転する、という戦略が百貨店には取れません。なぜなら、百貨店がそこにあることで街がつくられてきた歴史があるから。街の重心を自ら決めてしまった重力のような存在だから、安易に動くことはできない。この不自由さこそが、百貨店を単なる商業施設ではなく、地域のインフラとして機能させてきた理由です」
地元の個性を尖らせる編集力
地方百貨店の最大の特徴として、若杉さんが挙げるのが「地域性」です。全国の銘菓などをそろえる一方で、その土地で作られた商品が堂々と並ぶ光景は、地方百貨店ではごく当たり前だといいます。そこに秘められているのが、百貨店が長年かけて培ってきた「編集力」だそう。
「地方百貨店は、その地域を映す『小さなショーケース』のような存在です。売場を歩けば、どんな銘菓が愛され、どんな人たちが暮らしているのかが一目でわかります。例えば、天満屋の岡山や倉敷、福山などの店舗では地場産業であるジーンズブランドが他の地域よりも大きな面積を占め、福岡の岩田屋本店では明太子売場の圧倒的な迫力に驚かされます。これらは、百貨店が長年その土地で商いを続け、街や人の空気感を読み取ってきた結果です」

こうした編集力は、地元の人にとっても重要な意味を持ちます。「百貨店で買えば間違いない」という信頼感は、贈答文化とも深く結びついてきたと若杉さん。
「地方では、行政が何か表彰する際の副賞が地元百貨店の包装紙で包まれて届くことも多いです。その包装紙があるだけで、中身の価値が保証され、格が上がる。それだけ百貨店という存在が、地域の文化的な基準点として認識されているんです」
「百貨店が認めた」というお墨付きや、地方百貨店の編集力が新たな芽を育てるケースも出てきています。
「そこまで名が知れ渡っていない地元メーカーであっても、百貨店に出店しているという実績が最大の信頼となり、そこから全国区へと羽ばたいていくケースは少なくありません。また、百貨店自らが『地域の商社』として動き、地元の優れた産品を都市圏や海外へ繋いできた例もあります。百貨店は地域の才能を育てるインキュベーターとしての顔、あるいは地元の良いものを外へ売り出していく商社としての側面も持っていると思います」
タイパや効率の対極にある「丁寧さ」がエンタメになる
地方百貨店の課題としてよく挙げられるのが、少子高齢化や老朽化。地域の人口減少や高齢化が進むなかで、百貨店を日常的に利用する層は縮小し、かつてのような家族単位の消費や贈答の機会も減りつつあります。さらに、建て替えに膨大な費用がかかることも珍しくなく、昔からある店舗で営業を続けているのが実情です。そういった課題に対して若杉さんは、「百貨店の魅力が、今の時代に合った形で伝えられていないこと」にこそ、突破口があると考えています。
「若い世代にとって、百貨店の対極にあるのはECサイトやディスカウントストアです。それらと比較した時、百貨店の『過剰なまでの丁寧さ』は、もはや1つのエンターテインメントになります。例えば、贈答品の掛け紙や祝儀袋にその場で手書きしてくれる筆耕サービス。墨の香りが漂い、美しい筆跡で自分の名前が記されていく数分間。デジタルネイティブの若者にとって、これほど贅沢なアナログ体験はありません」
重厚なシャンデリアや丁寧な接客が息づく空間、そして屋上にひっそりと佇む神社。百貨店にとって当たり前の光景は、視点を変えれば特別な「体験価値」に反転します。
「この価値は、すでに世界基準の観光資源になりつつあります。パリのボン・マルシェやロンドンのリバティがそうであるように、日本の百貨店も建物自体が歴史的価値を持つ文化財であり、最高のホスピタリティーを提供する体験型ミュージアムといえる存在です。実際、この新たな価値には、日本人よりも海外からの観光客の方が早く気づき始めています。日本橋三越本店や大丸心斎橋店を訪れる外国人観光客の姿は、その象徴といえるでしょう。特に都市部の百貨店は『街を代表する店』にとどまらず、『日本を代表する店』として、国を象徴するものが集まる場所へと進化していく余地があるのではないでしょうか」
20XX年の百貨店は、ハレもケも楽しむ全世代の居場所に
若杉さんは、未来の百貨店は「何を売るか」以上に「どんな場であるか」が問われるようになると予測します。それは、これまでの格式を保ちつつ、ショッピングセンターや道の駅のような「全世代の居場所」としての機能も合わせ持つ姿です。
「私が地方で百貨店をゼロから作るとしたら、アミューズメント性や文化活動の場を備えた、ハイブリッドな場を目指します。日常の買い物と、ハレの日の体験が混ざり合い、お年寄りから中高生までがそれぞれの目的で滞在できる場所。百貨店という装置のうえに、現代のニーズに合わせた多様な機能を載せていくようなイメージです」

そのアップデートの際、最も大切にすべきなのは「百貨店独特の空気感」だと若杉さん。
「機能が変わっても、重厚感のある建物のなかで『いらっしゃいませ』と声をかけられる、あの背筋の伸びる空気は残してほしい。子供の頃に感じた『なんだかここは特別な場所だ』という記憶は、大人になっても来店する動機になります。百貨店が『買い物に行く場所』から『街を楽しみ、地域の誇りを確認する場所』へと進化し続ければ、その存在意義はさらに深まるはずです。街に百貨店があるということは、その街に誇りがあるということですから」
【編集後記】
取材のなかで、百貨店には「その地域が必要としているものは何か」が具現化されてきたし、これからもそうしてほしい、というお話がありました。「必要としているもの」は特定の商品やブランドかもしれないし、機能性やアミューズメント性かもしれないし、あるいは「地域の誇り」という大きなものかもしれません。全国にある百貨店が多様な姿をしているのは、それぞれの地域にとって必要なものを百貨店が独自にキャッチし、体現しようとしてきたからだということを改めて実感しました。
そうなのです、百貨店といっても実際の姿はすごく多様ですし、「百貨店らしさ」といわれるものにも想像を超えて多様な側面があるはずです。そしてそこには、百貨店のこれからをおもしろく考えていけるようなヒントがあるのではないでしょうか?
そんな視点からこの連載は始まりました。「百貨店にとって当たり前のことが外から見たらおもしろく、でもそのおもしろさはあまり知られていない」。若杉さんもおっしゃっていたこの視点をもち、さまざまな分野の目利きと探しにいこうと思います。
(未来定番研究所 渡邉)
第1回|