地元の見る目を変えた47人。


2023.10.30
わかりあう

多様性が謳われる社会となった今、私たちは「わかりあえない」ことを理解しつつも、「わかりあう」ために悩んでしまいます。そこで今回ご登場いただくのは、耳の聴こえない親をもつ、聴こえる子どもであるコーダの五十嵐大さん。幼い頃に差別や偏見を目の当たりにしてきたからこそ、現在のような多様性が謳われる社会をどう捉え、どんな課題を感じているのでしょうか。また、誰もが生きやすい世の中になるために、同じ社会を生きる私たちはどうあるべきなのでしょうか。多様性社会の今とこれからについて伺いながら、「わかりあう」について五十嵐さんと考えます。
(文:船橋麻貴/写真:嶋崎征弘)
五十嵐大さん(いがらし・だい)
1983年、宮城県生まれ。耳の聴こえない両親を持つ、聴こえる子どもであるコーダ(CODA:Children of Deaf Adults)として生まれ育つ。2015年よりフリーライターに。2020年10月、宗教にハマる祖母、元ヤクザの祖父、聴こえない両親との複雑な関係を描いたエッセイ『しくじり家族』(CCCメディアハウス)で作家デビュー。他の著書に『ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと』(幻冬舎)、『聴こえない母に訊きにいく』(柏書房)などがある。
X(旧Twitter):@daigarashi
多様性という言葉を使うことに、
満足してはいけない
F.I.N.編集部
五十嵐さんはコーダとしての生い立ちを生かして、社会的マイノリティの取材や執筆活動を行っています。多様性が謳われる社会となった昨今の状況について、どう捉えていますか?
五十嵐さん
正直、多様性という言葉が乱用されていると感じます。たしかに、多様性やダイバーシティという言葉が出始めた頃は、社会的マイノリティに対して理解が深まっていくのではないかという期待感がありました。だけど最近は、「多様性って言っておけばいいんでしょ?」というような空気が漂っている気がして。それはメディアや企業、個人でもそう。多様性という言葉を使うことで自分は理解している側にいるという、ポジションを取っている人が多いように思います。多様性という言葉を免罪符にしているというか。
数年前、「障害」という言葉にも同じような違和感を抱いたことがあります。「障害」って、一般的には漢字を使って表記するじゃないですか。だけどメディアや企業によっては、「害」という漢字をひらがなにして「障がい」と表記したり、または別の漢字を用いたりして。なぜ違和感を覚えたかというと、それよりも先にやるべきことがあるのではないかと思ったからです。表記を変えただけでは、当事者の人たちの生活は変わりません。本来、僕たちが変えるべきことは「障害」の表記ではなくて、社会制度が整っていない「現状」なんですよね。

F.I.N.編集部
言葉を変えるだけで満足したらいけない、と。
五十嵐さん
それは多様性に対しても同じで、言葉だけ使って満足してはいけないんです。もちろん、言葉が一般的になることで社会の空気やムードを牽引することは、たしかにあります。だから言葉は正しく理解して使うことが大切。社会の中にはさまざまな人がいて、そうした他者に対して理解を深めるという意図を持って、多様性という言葉を使ってほしいなと思います。
F.I.N.編集部
言葉だけが先行しているような状況がある中で、五十嵐さんの幼少期と現在で、社会の変化を感じることはありますか?
五十嵐さん
僕が子どもの頃はあからさまな差別や偏見がたくさんありました。近所の人から「障害のある親から生まれた子どもはろくな大人にならない」と直接言われたこともあったし、手話で話していたら指を差して笑われたことも……。そういう目に見えてわかる差別と偏見は減ったとは思います。

F.I.N.編集部
あからさまな差別や偏見が減ったのはなぜだと思いますか?
五十嵐さん
最近とくに感じるのは、今の10代・20代の方々の価値観に、当たり前に多様性が染みついていること。男性がメイクやネイルするのも普通のことになっていますよね。僕が若い頃だったらバカにされていたことが、その世代の方々にとっては当たり前のことになっている。これはセクシュアリティや、障害・病気のある人たちに対してもそう。そういった若い世代の声や考え方が社会に浸透してきていて、それに伴い、上の世代も変化しつつある。すると、社会にも大きな変化が訪れました。例えば、ろう者・難聴者と聴者が電話でコミュニケーションを取れるようにした〈電話リレーサービス〉が生まれたり、体を思うように動かせない人のために〈分身ロボットOriHime(オリヒメ)〉が開発されたり。「この社会にはさまざまな人が存在していて、そういった人たちを取り残さない」という考え方が一般的になるに従って、差別や偏見のない世の中が少しずつ実現できているのかもしれないと感じます。
誰かの希望を奪わないため、
わかりあえると言い続けたい
F.I.N.編集部
今回の特集テーマは「わかりあう」です。五十嵐さんは「わかりあえない」と痛感するシーンはありますか?
五十嵐さん
正直、わかりあえないと感じることはあります。「差別はなくならない」「差別があるのは当たり前だろう」と冷笑するような人とは、意見を交わしても平行線のままだったりするので。だけど、このインタビューだから言いますが、人と人はわかりあえないとは言いたくないです。なぜかというと、自分をわかってもらえないことで追い詰められて、明日にでも死んでしまう人がいるからです。もしかしたら、僕が今話している目の前の人が実は追い詰められているかもしれない。そんな人を前に、「結局人と人はわかりあえない」と口にしたら絶望してしまう。だから僕は人と人はわかりあえる、そう言い続けたいです。

F.I.N.編集部
「わかりあえる」と伝えることは大事なんですね。
五十嵐さん
わかりあえないと言えるのは、誰かにわかってもらわなくても生きていける人の特権なんですよね。ある側面では僕もそっち側だと思いますが、だからといってわかりあえないと言うのはあまりにも乱暴。マイノリティであることで孤立し、自分はおかしいのではないかと悩み、自死を選んでしまう人がいる現実を前にして、わかりあえないとは僕は言えないです。
F.I.N.編集部
では、人と人がわかりあうためには、何が必要でしょうか?
五十嵐さん
想像することだと思います。ただ、相手のことを知らないと想像するのにも限界があるので、当事者の声に耳を傾けることがすごく大切だと思います。SNS上ではたびたび、特定の属性の人たちについて議論されることがありますよね。でも、肝心の当事者の姿があまり見えず、擁護派と否定派にわかれた非当事者がぶつかっていることが多い。当事者が置き去りにされてしまっているんです。それはものすごく乱暴なことだと思うし、体感が伴っていないからどこまで説得力があるのかもわからない。だから、やはり当事者の声を聞かないといけないと思うんです。著書の『聴こえない母に訊きにいく』で聴こえない母に話を聞きに行った時がまさにそうでしたが、一番身近な母のことを僕は何もわかっていなかったんです。全然知らないことだらけだったし、自分が想像していたことよりも遥かにいろいろなことがあった。文献を読んだり、ネットで情報を集めたりするのもいいですが、当事者から生の声を聞くことに勝るものはない。そう実感しました。
それから属性で決めつけないことも大切。誰か一人の話を聞いただけで「●●の人はこうだから」と雑な一般化をしない。主語を大きくしないというか。その属性の人全員を理解したつもりにはならないようにすることも大事だと思います。
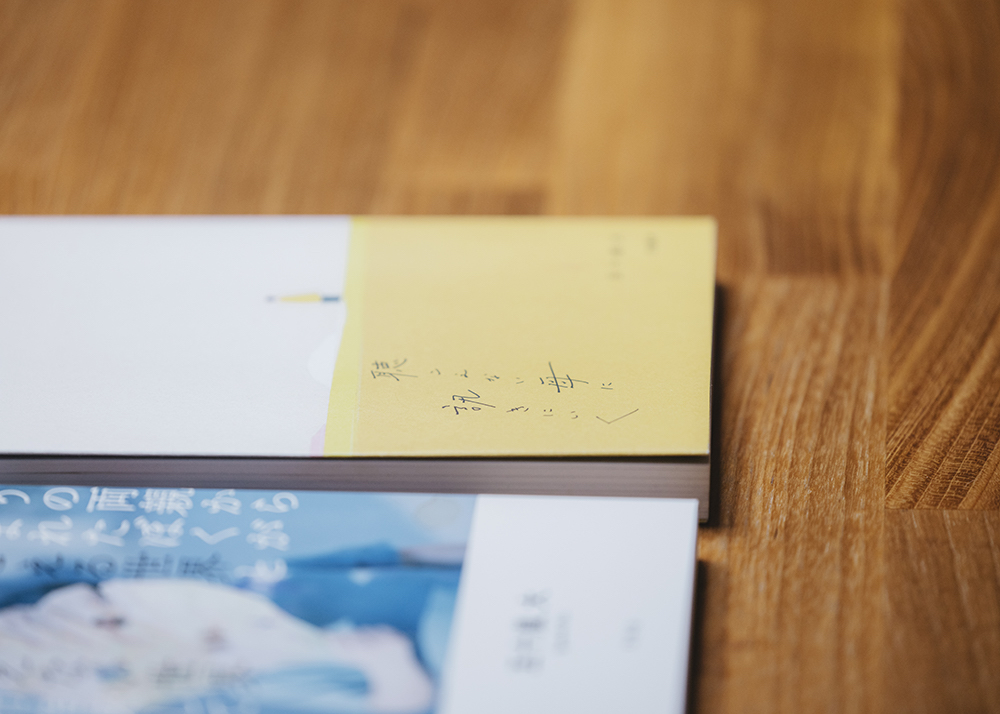
F.I.N.編集部
当事者の声に耳を傾けることを大切にしたいと思いつつも、実際にご本人を前にしたら萎縮しちゃいそうです……。
五十嵐さん
僕もそういう時期があったので、めちゃくちゃよくわかります。だけど、難病児を育てるお母さんに言われた言葉にはっとしたんです。その子は車椅子に乗っていたんですが、外に出かけると近所の人たちがみんな目を逸らすそうなんです。ところがある日、小さな女の子が駆け寄ってきて、「どうしていつも車椅子に乗ってるの?」と話しかけてきたと。僕はそれを聞いて不躾なんじゃないかと思ったんですけど、お母さんはすごく嬉しかったとおっしゃるんです。自分たちを腫れ物に触るように扱う人が多い中、純粋な疑問を持って話しかけて来てくれたことが嬉しかった、子どもでも大人でもわからないことは聞いてほしい、と。そこから僕は純粋に疑問に思ったことは何でも聞くようになりました。ただし、当事者に繰り返し説明させることは避けなければいけません。ここで大事なのは「腫れ物扱いされなくて、嬉しかった」という部分。少し調べればわかることくらいはちゃんと勉強した上で、同じ人間としてフラットに接し、もっと知りたいと思うことは臆することなく聞いてみる。それが必要なんだと思います。実際、当事者の方々も、自ら理解しようとアクションを起こしている人たちに怒りを向けたりしません。むしろ好意的。当事者への過剰な配慮は、わかりあう時の隔たりになり得るんですよね。
F.I.N.編集部
わかりあう社会にするためには、まずは私たちがアクションを取ることが大切なのですね。
五十嵐さん
待ちの姿勢でいたら何も変えられません。ただ、繰り返しになりますが、マイノリティの人たちは生まれてから今に至るまで、100回や200回じゃ足りないくらい同じことを説明してきているんですよね。どんなマイノリティなのか、この社会に何が足りないのか。そんな質問を散々されて、説明を繰り返してきているわけです。なかにはもううんざりしている人もいるだろうし、疲れ切っている人もいる。だから、マイノリティの人たちを理解するためには、マジョリティの人たちが率先して勉強することも大事です。
F.I.N.編集部
そうしたアクションを取りたいけどどうしたらいいかわからない。そんな人も少なくないかもしれません。
五十嵐さん
興味関心を持っている時点で、能動的なアクションになっていると思います。テレビやネットでニュースを見たり、マイノリティの人たちについて調べたりするだけでも、何もしないより遥かにいい。それを行う前と後では、自分の身の回りにバリアフリー不足を感じたりと、見える景色が変わっているはずなので。マイノリティの人たちを理解するのは、まずは知ることから。自分の視野を広げることで、少しずつ社会が変わるきっかけになると思います。
F.I.N.編集部
ご著書の中で五十嵐さんは、障害のある人を「守る」のではなく、「ともに生きる」ことが大事だと書かれていました。それもわかりあうために必要な考えになりそうですね。
五十嵐さん
これは僕自身の経験から言えることなのですが、障害のある人に対して過剰な優しさを向け、善意で何もかもやってしまうことは、一つの差別になると思っていて。以前、耳の聴こえない友人たちと居酒屋に行った時、店員さんを呼んだり、注文したりと、何から何まで率先してやったことがあるんです。そうしたら仲の良い友達から、「耳が聴こえない私たちに代わって、いろいろやってくれてありがとう。だけど、指を差して注文できるし、手を上げて店員さんを呼ぶこともできる。私たちからできることまで奪わないでほしい」と言われたんです。その時、はじめて自分の浅はかさを知りましたし、それこそ無意識の差別だったんじゃないかって。
思い返してみたら、耳の聴こえない母に対しても同じことをしていたんです。パートに出たいと言われた時は反対したし、地域の催しに代わりに参加したりして。僕はずっと「守ってあげなきゃ」と思っていたんですけど、母はそんなに弱くなかったんですよね。むしろ僕自身が守ってもらっていた。そう気づいてからは、障害のある人への一方的な気持ちはなくなりました。僕も守るけど、僕のことも守ってもらいたい。横並びで同じ風景を見ながら、支え合って一緒に生きていきたい。今はそう思っています。

世界を見る目を養えば、
友人や自分をも救えるように
F.I.N.編集部
五十嵐さんは耳の聴こえない両親を持つことから、幼い頃は「普通」に憧れていたそうですね。多様な世の中となった今では「普通」の概念自体が揺らいでいる気がします。そんな今、幼い頃の自分にどんな言葉をかけたいですか?
五十嵐さん
たしかに、健康な男女が結婚して子どもを持って家庭を築くというのが、かつての「普通」の家族のかたちでした。でも今ではそれだけが幸せのかたちじゃないと、多くの人が知っていますよね。当時はこんな社会になるとは思いもしなかったので「普通」に憧れていたし、「普通」じゃないからやりたいことができないと思い込んでいました。だけど今は、好きなように生きても弾かれることもないし、むしろ好きなことをやっている方がいいくらいの世の中になりました。そんな今、幼い頃の自分に何か言ってあげられるなら、「自分のやりたいように、好きなように生きていいよ」ってことですかね。
とはいえ、僕は大人になると、役者を目指したり、フリーターをしたり。その後、フリーライターになって、作家にもなりました。思いのほか、自由に生きてきましたね(笑)。

F.I.N.編集部
社会的マイノリティの取材や執筆活動を通じて、五十嵐さんご自身の学びになったことはありますか?
五十嵐さん
当事者の方に会ってお話を聞くことで、新しい視点が僕の中に少しずつ増えていきました。今も全然足りていないけど、いろいろな人の視点や価値観を知ることで、世の中を見る解像度が格段に高くなったと思います。それが何の役に立つかと言ったら、それこそものを書く時もそうだし、街を歩いても困っている人に気づくかもしれない。あるいは身近な友人を助けられるかもしれない。それが最終的には自分自身を助けることにもなると思っています。世界を見る目を養うと、自分も生きやすくなる気がするので。
F.I.N.編集部
多様性が謳われるようになって久しい世の中ですが、5年後の未来ではどんな社会になっていると思いますか?
五十嵐さん
次の時代の空気を作るような10代・20代の人たちに、すごく期待しちゃっている部分があるんです。今、「多様性」「ダイバーシティ」など、未来の社会のために試行錯誤しているじゃないですか。それに対して文句を言う人もいますが、次世代を担う10代・20代の人たちは自然とそれを取り入れているんですよね。だから5年後、10年後は、「多様性」「ダイバーシティ」が議論に上がらないくらい当たり前になっていて、それらを否定するような人に「ダサくない?」と言いながら、社会を牽引してくれる気がします。もちろん、その世代に丸投げするのではなく、自分たちの世代でも一人ひとりができることをやらなきゃいけません。僕の場合は、社会的マイノリティにまつわる文章を書いたり、今みたいに取材を受けたり。そうして5年後、10年後は、「多様性」「ダイバーシティ」という言葉を使う場面がないくらいの社会になっていればいいなと思います。

【編集後記】
「人と人はわかりあえないとは言いたくない」。取材中、静かに発せられた五十嵐さんの力強いその言葉に、胸が熱くなる思いでした。それと同時に、日頃、自分自身が何気なく発している「わかる」という言葉の重さを突き付けられたような気がしました。
そもそも私たちは一人ひとりが異なる人間で、それぞれが違った世界を見ています。お互いを100%理解することは到底できませんが、それでも他者の声に耳を傾け、想像し、自分自身の世界を広げていくことで、少しでも解像度の高い「わかる」を増やしていくことができたなら、その先には他者にも自分自身にも優しいまなざしを向けられる。そんな温かな社会が待っているのかもしれません。
(未来定番研究所 岡田)