


少しでも誤った発言や対応をしたものなら、ただちに糾弾され一発退場となりかねない昨今。過去の発言を掘り起こして非難する様子も見られ、年々「ゆるさない社会」が加速しているように思います。一方で、自分や他人を許すことの重要性を見直し、寛容さを大切にする動きも広がりを見せています。あらゆる場面で寛容さが増すと、私たちの生活はどのように変わるのでしょうか。F.I.N.では、この「ゆるす社会」を実践している人々を取材し、彼らの視点から未来の社会の在り方を探っていきます。
今回お話を伺うのは、北海道にある福祉法人〈浦河べてるの家〉の創設メンバー・向谷地生良さん。精神障害を抱える人たちとともに、自分の「生きにくさ」を一緒に研究し合う「当事者研究」を創案し、さまざまな取り組みを行っています。そんな向谷地さんに、「ゆるす社会」の実現に必要なことを教えていただきました。
(文:船橋麻貴/イラスト:ワタナベケンイチ/サムネイルデザイン:小林千秋)
向谷地生良さん(むかいやち・いくよし)
〈浦河べてるの家〉理事長、北海道医療大学名誉教授、ソーシャルワーカー。1955年青森県生まれ。大学卒業後、浦河赤十字病院の精神科専属のソーシャルワーカーとして赴任し、1984年に〈浦河べてるの家〉を設立。著書に『べてるの家の非援助論』(医学書院)など多数。
生きやすい社会には、「和解」が必要
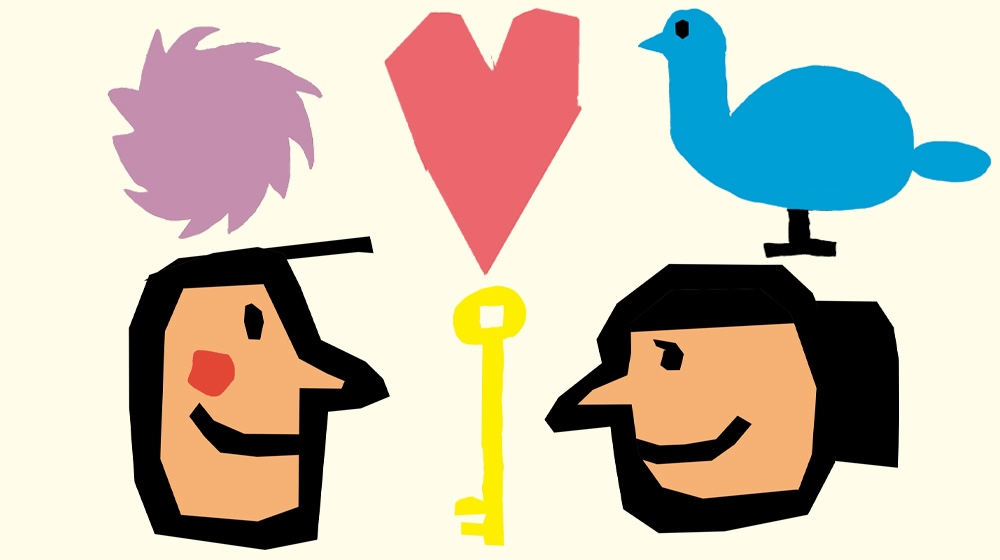
F.I.N.編集部
メンタルヘルスの領域で50年近くソーシャルワーカーとして活動されている向谷地さん。「ゆるさない」と「ゆるす」の間で揺れ動く昨今の社会について、どのように感じていますか?
向谷地さん
人間関係においても悩んでいる人が多く、社会全体で生きる苦悩が最大化した状態になっていると感じています。分断や排除といった動きが多く起こる今、私たちに必要なのは「和解」なのではないか、と。
F.I.N.編集部
なぜ「和解」が必要なのでしょうか?
向谷地さん
私たちが向き合っているのは、いわゆる心の病。症状に対して医学的な診断によって投薬治療なども行いますが、根本的に必要なのは「関係性の回復」で「自分との関係」と「他者との関係」ではないかと思うんです。なぜかというと、普通、病気になると周りに心配されたり、同情されたりするんですが、統合失調症やうつ病、アルコール依存症などの心の病の周辺には、不安や苛立ちがあり、関係の危機が起きるからです。私の駆け出しの頃の話を例に挙げると、アルコール依存症を抱える旦那さんは、子供の貯金を使い込み、奥さんから「お酒をやめてほしい」と懇願されても、当人はやめたくても止まらないわけです。家族も支援者の私も何度も裏切られ続けました。
ある時、酔い潰れて暴れる旦那さんに絶望した奥さんが包丁を持ち出した場面に出くわしたことがありましたが、私は奥さんの気持ちがわかった気がしたんです。メンタルヘルスの専門家である前に、私も人間として腹が立って仕方なかった。ですが、よく考えたら、四方八方から責められ続けながら、お酒を手放せない自分と付き合わなければならない旦那さんだって、しんどいですよね。みんな「お酒から離れてほしい」と願っているのに、本来の自分の気持ちとは違うところで振り回されている。そう気づいた時、正直に自分の気持ちを伝え合って「和解」する必要があると感じたんです。家族や私たちとの間に新しく関係性を築くことで、回復の土台になるんじゃないか、と。
F.I.N.編集部
生きる苦悩から抜け出すには、他者や自分を「ゆるす」のではなく、「関係性を築く」ことが大事なのですね。そのために、自分の弱さをさらけ出す必要があると。
向谷地さん
ええ。実際、私たち〈浦河べてるの家〉では「弱さの情報公開」が1つのキーワードになっています。お互いの「関係の回復」のためには、「さらけだす」というほど大げさに考えなくても、自分の弱い部分や些細な困りごとをみんなで持ち寄って正直に伝え合って、そのうえでお互いにどう助け合うかが、日常の中で語られ、共有される組織文化が大切になってきます。
F.I.N.編集部
私たちは「自分の問題は自分で解決しなきゃ」と思いがちですが、周りのみんなで弱さを共有するのはなぜですか?
向谷地さん
そもそも人は、1人では生きていけない利他的で社会的な存在です。しかし、いつの間にか私たちは、人の手を煩わせない、迷惑をかけないことを自立だと考えるようになってきました。そのような自立感が、結果的に孤立を生んでいるように思います。その点も、心の病を経験した人たちの回復のプロセスに学ぶことが多いですね。早く病気を治して、家族に迷惑をかけず自立しようと頑張る人は、ほとんどうまくいかないんです。半面、自分の力だけで暮らすのは無理だと気づき、むしろ身近な人とのつながりや社会的な資源やサービスに、前向きに「依存」して暮らすことの大事さがわかってくると生きやすくなるわけです。それが、成長的な回復につながります。それを私たちは「降りていく生き方」と言っています。それまでの上昇志向的な生き方、暮らし方ではなく、人と自分に優しい「降りていく生き方」に切り替わることで病も癒される。そんな気がしています。
これは私たちにとっても同じ。例えば私がソーシャルワーカーとして知識や技術を磨き、人格的にも尊敬される有能な支援者になろうと頑張っているうちは、まったくうまくいきませんでした。むしろ、先ほどの例のように、行き詰まって現場に立ち尽くす経験をした時にそれ以上の過酷な現実を生きてきた当事者や家族に学ぶことを覚えましたし、自分の弱い部分を認め、人に相談して「弱さの情報公開」をすることで人間的な成長にもつながった。こうして私たちは自分を開き、社会的に失敗したり、行き詰まったりしている経験を持つ人たちに学びながら、自分や社会を常に更新していく。生きやすい社会を実現するためには、こういうあり方が必要だと思います。
自分の弱さは笑い飛ばし、外在化する

F.I.N.編集部
〈浦河べてるの家〉では自分の弱さと向き合う「当事者研究」を行っていますが、そのなかで大切にしていることは何ですか?
向谷地さん
私は、たくさんの「弱さ」が積みあがって生まれるのが「強さ」だと考えています。だから、私たちは、生きる素材としての「弱さ」を大事にしてきました。それが「当事者研究」では、貴重な研究素材でもあるわけです。深刻で持ちきれない悩みや心配ごとも「一緒に研究しよう」と考えることで、性質が変わり、持ちやすくなるわけです。そういう意味で当事者研究に大切なのは「遊び感覚」です。自分の病に自分の実感をともなったオリジナルな「自己病名」をつけることもそうです。自分の苦労を笑い飛ばすことで、問題と距離が生まれますし、新たな発想にもつながります。
F.I.N.編集部
自分の「問題」を笑い飛ばす研究は、どうして生まれたのでしょうか?
向谷地さん
「当事者研究」が生まれたのは2001年。当時私たちは、次々とトラブルを起こす統合失調症を抱える1人の若者とどう向き合えばいいかわからず、非常に行き詰まっていたんです。本人も私たちも疲れ果てていたんですが、その時に、ふとつぶやいた「一緒に研究しない?」ということから始まったのが当事者研究です。彼が起こす問題行動を「爆発」と称して、そのメカニズムをみんなで研究したり、あるいは「爆発」のいい点をみんなで考えたり。問題や弱さに対して「遊び」や「笑い」を交えて研究し、批判を承知で発表してみたら会場は大爆笑だったんです。厳しい現実を目の前に、みんなで一緒にお腹をかかえて笑ったり、面白いと言い合ったりすることは、おそらく問題解決には至りません。ですが、彼が私たちの仲間であることを再認識できたし、彼自身も顔を上げてくれた。それだけで十分なんじゃないかと思いました。
F.I.N.編集部
向谷地さんご自身は、「当事者研究」から学んだことはありますか?
向谷地さん
それは、「苦手な人」「嫌いな人」を大事にする、ということですね。好きにならなくてもいい、そのままでいい。だけど、「大事にする」ということです。私や〈浦河べてるの家〉の成長を支えたのは、自分にとって「苦手な人」「嫌いな人」という存在だったんです。そもそも私は人が人を「ゆるす」という考え自体が、少し傲慢なのではと思っているんですが、「当事者研究」を通じて教えられたのは、この世に無駄な人はいないということですね。「当事者研究」をしたからって、そう簡単に病気がよくなるわけではないし、依存を断ちきれるわけでもない。でも、多くの倒れていった仲間の残した貴重な研究遺産である「苦悩のパターン」や「生きづらさのメカニズム」など、彼らから学んだことは多かった。だから私は、仲間がつないでくれた学びを生かせるような社会にしたいと思っています。
「対話」によって、他者も自分も開く

F.I.N.編集部
「当事者研究」を私たちの生活に取り入れることはできるのでしょうか?
向谷地さん
私たちは「当事者研究」を語る時、「対話実践」の1つとして紹介しています。この「対話」は、実はすでに私たちのなかにあるもの、そのなかに私たちは生れ落ちるといわれています。そして、空気みたいな存在だからこそ、私たちから「対話」を取り上げたら生きられません。ですから、当たり前すぎてその大切さを自覚しないまま生きていることが多い。つまり、私たちにとっては欠かすことのできない生命的な営みなんですよね。だから、改めて「対話」に着目してみるといいと思います。
F.I.N.編集部
なぜ今、「対話」を見直す必要があるのでしょうか?
向谷地さん
私たちは科学を発達させることで、論理的なロジックで社会の問題を解決しようとしてきました。しかし、期待された薬物療法やさまざまな心理的な介入をもってしても、心の病の本質と背景の理解や治療方法は確立されていません。そのなかで注目されるようになってきたのが「対話」です。とくに私たちは、当事者研究の取り組みから、お互いに自分を開き、「気心が通じ合う」感触、「心が温まる」実感の大切さを感じるようになりました。そこに至る大事な部分が誰もが持っている「弱さ」であり、「対話」なのだと思います。
F.I.N.編集部
「対話」では、どんな工夫をしたらいいでしょうか?
向谷地さん
まず、私は「悩む」という言葉は使わないようにしています。「悩み」という言葉は、どこか問題と自分が同一化(内在化)している印象があります。実は、それが一番、心身に堪える気がします。例えば仕事へのやる気が起こらない場合、「最近、エンジンがかかりにくい」という言葉を使ってみたり。そうやってユーモアを交えて他者に届けることで、相手と「その車、ガソリンちゃんと入ってんの?」「オイルは?」「定期点検は?」などとワイワイする。これは、「外在化」ともいわれるものです。「対話」というのは、お互いに考え方も、立場も、目的も違う者同士が行い、ともに暮らす模索の中で見出された古代人の知恵に源流があるんですけど、この「対話」という生命的な営みが持つ可能性を、現代になって実にさまざまな人たちが活かす試みをしています。当事者研究は、その1つだといえます。「弱さの情報公開」もその当事者研究のアイデアの1つで、自分の経験にまつわる出来事を、あえて「感情」を脇において「情報」として共有することで、互いに学び合い、活かし合い、改めて「感情」を添えることで対話が熟成する、そんなイメージを持っています。
「弱さの情報公開」は、ちょっと勇気のいることかもしれません。だけど、こうやってちょっと工夫を凝らすことで、相手も受け取りやすいし、自分ごととして考えやすくなる。具体的な解決には至らないかもしれないけれど、困りごとや悩みごとの種に近づけるはずです。
F.I.N.編集部
「対話」を大切にしながら自分の「弱さの情報公開」をすると、どんな変化が起こりますか?
向谷地さん
今から40年前、精神科に入院した経験のある若者たちと昆布の下請けの仕事を始めた時のことです。1人のメンバーが、仕事中にも関わらず頻繁にタバコを吸いにいなくなるわけです。あるメンバーは来たと思ったら「帰る」と言い出し、別のメンバーは「おはよう」と挨拶したら「そんなこと言われる筋合いはない」と怒り出す。気がつくと、仕事のメンバーがどんどん減っていき、職場の空気も悪くなったんです。そこから生まれたのが「弱さを絆に」という理念と、「弱さの情報公開」というアイデアです。一人ひとりが、「仕事中に、『帰れ』という声が聞こえたこと」など自分に起きていることを話すと「そうだったんだ」と、お互いが理解しあって助け合うようになったんです。
それから、私たち〈浦河べてるの家〉の理念には、「今日も明日も明後日も、ずっと問題だらけ。それで順調!」というものもあります。実際、「弱さの情報公開」では、問題はすぐに解決しないでしょう。しかし、問題の数だけ「対話」ができるし、「明日、我が身に降りかかるかもしれない」と、自分ごととして問題と向き合えるようになる。そうやってお互いに前向きな関心を寄せ合いながら、もう少しやさしい社会になっていけたらいいですね。
【編集後記】
自分や他人をゆるすことが困難な時、そこにはしばしば「わかることができない」という辛さがあります。ゆるしがたいものが自身や他者の中にあると思い悩んで、なぜ自分は、なぜあの人は、と考えてしまう。同時に、それが何かしらの努力によって「いつかわかる」「いつか解決できる」と信じるのをやめられない。ゆるせないけどゆるしたい、とはそんな混乱から抜け出せない状態なのかもしれません。
今回、そのような苦悩を「外に出してみる」という方法を向谷地さんに教えていただき、私は驚くと同時に胸がすく思いでした。また、外在化させることでその対象に「前向きな関心を持てるようになる」とおっしゃっていたことも印象に残っています。なるほど、人と問題とを切り離して前向きに考えていく姿勢は、わからないことだらけの自分や他人と自然に付き合うための支えになりそうです。
(未来定番研究所 渡邉)