


古くから日常的に親しんできた、和歌や短歌、俳句、詩などを含む「詩歌」というもの。とくに近年は、日本文学における詩歌を「よむ(読む・詠む)」ことが再燃しているように思います。インターネットやSNSの普及とともに、誰もが「よむ」ことを表現できるようになったこの時代を、編集者たちはどのように見つめているのでしょうか。
今回お話を伺ったのは、〈ナナロク社〉代表取締役・編集者の村井光男さんと、〈書肆侃侃房〉(しょしかんかんぼう)の編集者で、短歌ムック『ねむらない樹』の編集長を務める藤枝大さん。短歌や詩を「よむ」ことが、ある種のムーブメントになったこの時代について、両氏の対話を通し再考します。
(文:倉本亜里沙/イラスト:竹井晴日)
村井光男さん(むらい・みつお)
編集者。出版社代表。2008年ナナロク社を創業。谷川俊太郎『あたしとあなた』、木下龍也『オールアラウンドユー』など詩歌の本を中心に、川島小鳥『未来ちゃん』(講談社出版文化賞)、森栄喜『intimacy』(木村伊兵衛写真賞)、『岡﨑乾二郎 視覚のカイソウ』ほか、写真集・アートブックを刊行。これまでに同社より刊行したすべての本の編集、または制作を担当している。
藤枝大さん(ふじえ・だい)
編集者。書肆侃侃房に在籍。詩歌、人文書、海外文学を主に編集している。短歌ムック「ねむらない樹」(編集統括)、「現代短歌クラシックス」シリーズのほか、『ブンバップ』『起きられない朝のための短歌入門』『たましひの薄衣』『左川ちか全集』『葛原妙子歌集』『Lilith』『悪友』『うたうおばけ』『赤の自伝』などを担当。詩歌と海外文学の書店〈本のあるところ ajiro〉を2018年に立ちあげ、運営している。
2人が「詩歌の編集者」になった理由

F.I.N.編集部
お互いの最初の印象を教えてください。
村井光男さん(以下、村井さん)
藤枝さんは最初から優秀な方という印象で、実際に詩や海外文学への造詣がとても深く、熱意もある方です。『女人短歌』(濱田美枝子/著)ですとか、現代に通ずるテーマのある本など、良本を刊行し続けていますよね。 藤枝さんが編集する本を通して、今までは点でしか見えていなかったものが、一気に立体として見えてくるようで、いつもそのお仕事には注目をしています。
藤枝大さん(以下、藤枝さん)
ありがとうございます。私も村井さんは編集者の先輩として本当に尊敬しています。特に村井さんが編集した『頭のうえを何かが Ones Passed Over Head』(岡﨑乾二郎/著)を読んだときは、もう頭をぶち抜かれるようにびっくりしましたね。本の可能性というとチープな言葉になってしまうけれど、こんな風に岡﨑さんの思考を本という形にして世に問えるんだ、と。詩人や歌人の方、作家と共に歩みながら、その人の最も核に近い部分を掘り下げ、本という物体に丁寧に落とし込んでいく。完成する本はもちろんのこと、その作り方の過程もかっこいいんですよね。
F.I.N.編集部
お2人が詩歌の出版に関わるようになった動機やきっかけは何だったのでしょうか?
村井さん
〈ナナロク社〉を立ち上げた当時から「これからは詩の時代になる」という仮説を立てていました。というのも、僕らは言葉を使って生き、その恩恵をもらっているわけですが、文章や散文は便利な反面、言葉の下に人を従えてしまうというか、言葉によって支配される面もあるように感じていました。その枠組みから、いかに抜けるか、人を解放するような言葉ってなんだろうと考えると、それが詩なのではないかと思ったんです。そして、詩は絶対に世の中に必要なものだけど、今はそれほど大切にされていないように見える。その詩を大切にして届けることができれば、それが自分の勝負どころになるような気がしていました。 藤枝さんはどうですか?
藤枝さん
私は東欧圏などを中心に海外の詩や文学を刊行している、〈未知谷〉という出版社に入社したことが大きなきっかけでした。先輩方が本当に詩に詳しくて、国内外の詩を浴びるように吸収できる環境だったんです。そこである詩集の帯に、「この世界にはまだ、より良いことを選択しながら生きていく可能性が残されている」とあって。さらに帯の背には「太陽の下では全てが新しい」と。普通は購買につながるようなもっと分かりやすく売るための言葉が載るものだから「こんな帯ある!?」と、かなり衝撃を受けました。帯文自体がまるで詩のようで、詩集がどういうものなのか、体感したことを覚えています。
村井さん
詩歌は世界のネタバレを見せるというか、読む前と後で世界の見え方を変えてしまう力がありますよね。同じような信号機でもよく見ると青の点灯の微妙な色の差に気づいたら、もういつ見ても違う色に見えてしまうように、いろんなものの解像度を上げてくれる。僕にとっては、写真やアート作品と近い存在かもしれません。
谷川俊太郎さんの「芝生」という詩を読んだ時、心を掴まれるというか、これまで何度も目にした「幸せ」という言葉が、この詩を読んでいる間は、言葉を超えたイメージとして直接出会えました。自分が考えても行きつけなかったような、ある思考や思いを、谷川さんからもらったレンズみたいなもので覗くことができる。レンズをはずすともうわからなくなっちゃうのですが。でも、また、読むとわかる。
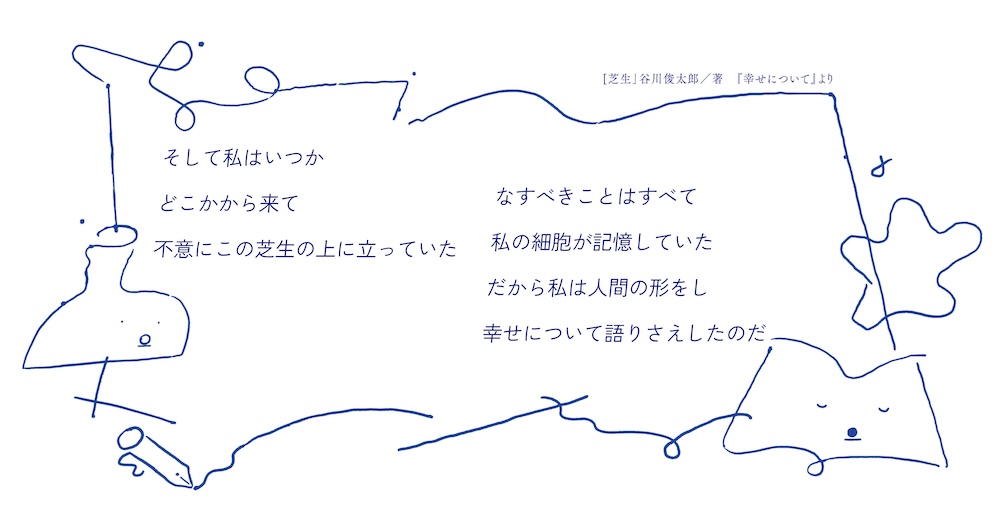
藤枝さん
私も学生の時に寺山修司や永瀬清子、左川ちかなどの詩歌に出会った時は、自分が生きている世界とはまったく別の何かが提示されたことに驚きがありました。最近編集を担当した『埃だらけのすももを売ればよい』の帯に「詩集とはある世界観の具現であった」という一節を載せました。この世には本当にさまざまな人間がいて、詩集もその数だけ別の世界観がそこにある、ということが刻まれた一冊なんです。であれば、詩集を介して別の人生に触れることも可能ですよね。その体験って、本当にかけがえのないものだと思うんです。
村井さん
そうですよね。普通に生活をする中で、自分に「この世界を感じる力がある」と信じられることって、実はめちゃめちゃ重要。「飲食店で1,000円を払った」自分は、客単価1,000円という数値として世界から見られているかもしれないけれど、同じ時間に自分は世界をまったく異なる目で見つめることができる。小さくて些細なものを拾うだけで、愉快に生きることが可能なら、その視点を貸してくれる詩歌はとても魅力的ですよね。
今、詩集が必要な理由。日常のポエジーが我々にもたらすものとは
藤枝さん
最近人文書を立て続けに編集したのですが、たとえ歌集や詩集ではなくても、詩の存在を随所に感じることがあるんです。たとえばパンクの抵抗の系譜を辿る人文書では、登場する重要人物が詩人であることも多くて。他にもカリブ海の思想を紹介する人文書のタイトルに、トバゴ島出身の詩人であるエリック・ローチの詩の一節が引用されていたり。文芸書に留まらず、あらゆる本のいたるところに詩は存在している。
私の大好きな『亡命ロシア料理』(ピョートル・ワイリ,アレクサンドル・ゲニス/共著)という本の帯には「キッチンにポエジーを」と書いてあるのですが、この帯文もとてもいいなと思っていて。あらゆるところに潜むポエジーを再認識しながら、丁寧に、味わうように本のかたちにして、世の中に届けていきたいと思うんですよね。
村井さん
詩集や詩そのものだけではなく、ポエジーがあらゆるところに拡散しているというのはよくわかります。だから、一時期それらを詩集としてまとめる必要がどこまであるのかなと考えることもありました。しかし、今はやはり詩人が詩を書き、それを編集者が詩集という形で世界に提示する必要があると考えています。
なぜなら、あまりに情報が多いから。これほど多くの言葉に、日常的に、それどころか四六時中さらされている時代はなかったのではと思います。次から次へと注ぎ込まれる言葉に溺れてしまうような実感は、みんな共有しているのではないでしょうか。
溢れてくる言葉から自分を守るために、情報から遮断され、潜るように詩や詩人と触れ合う体験が必要だと思っています。そのための装置としても、詩集はすごく重要なものなんです。

藤枝さん
私はSNS登場以降、時間が単線的というか、常にみんなが同じように刻まれる時間軸の中で生きてしまっているような感覚があって。なぜ、今詩歌が求められているかを考えると、もしかしたら人がそれに飽きているからなのかもしれないという感じもしますよね。
詩や短歌の言葉は、時間感覚がものすごく豊か。作品それぞれの中にある時間の流れや圧縮具合がまずちがうし、書かれた時期やその時代の言葉の使用法があって、さまざまな時間軸が今この時に生まれ直している。あらゆるバラエティーに富んだ時間が詩歌には詰まっていますよね。そう考えると、詩に触れることで、個々人の読者が時間を再定義できるような、そういううれしさとか喜びに満ちているのかなって気がします。
村井さん
時間感覚はまさに、そうですよね。日本語なら1,000年前の言葉でも、一応理解できるじゃないですか。歴史的にも複数言語、複数民族ではあるけれど、ある程度同じ土地に住み続けていて、なんとなく共有できるものがあるって、実はすごい好条件だなと思います。谷川俊太郎さんもよく、「日本語を足元から吸い上げて詩にしている」と話していて、今聞いていてどこか通じるものを感じました。
藤枝さん
正直詩歌ブームと言われてもよくわからないところもありますが、いろんな人が気軽に詩歌を作りたいと思ったり、実際作ってみたりしている状況は、とってもチャーミングだなと思います。
『埃だらけのすももを売ればよい』では、登場人物がどんどん詩人になっていくのですが、みんな突然、詩をやめちゃったりするんです。それを読んで、たしかに詩はいつ書き始めてもいいし、いつやめたっていいんだよなと。今はある意味『埃だらけのすももを売ればよい』的状況が起きていると言えるかもしれないです。誰もが今この時に詩人になってもいい、なれるんだ、という喜びがある。そんな状況は、すごく素敵だと思います。
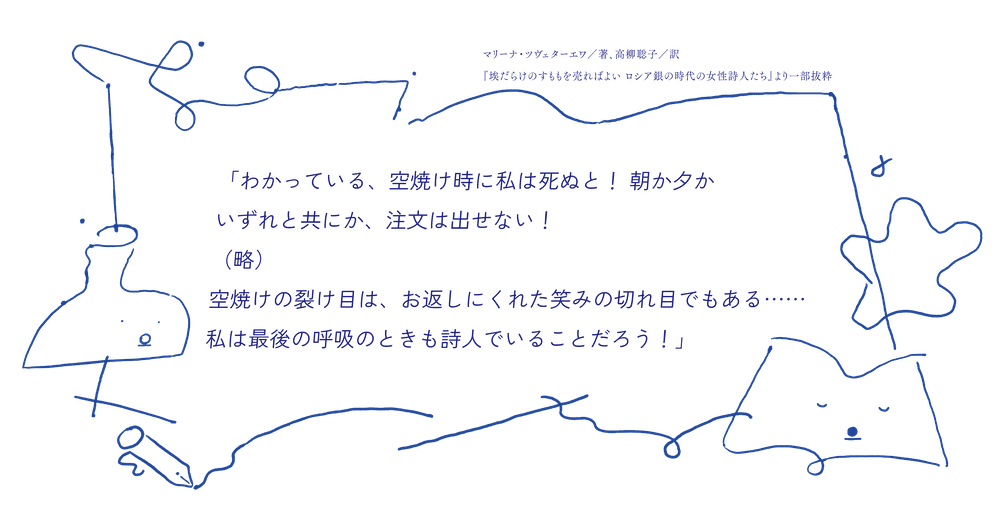
編んで届ける。詩歌の編集者と出版社、これからの在り方

村井さん
詩歌に注目する人が増えたのは、情報としての言葉が溢れ、その対極にある研ぎ澄まされた言葉へと向かう時代性もあるかと思います。ただ、独自のアイディアやそれこそ情熱で動き出して、自分たちがこの本を届けたいと行動する書店、出版社の存在は、やはり大きいと思います。
藤枝さん
そうですよね。詩歌がなかなか読まれなかったような時代から、例えば〈紀伊國屋書店 新宿本店〉の梅﨑実奈さんや〈葉ね文庫〉の池上規公子さんとか、詩歌を大事に思って届けてこられた方たちの営みが、この状況に至るまでの下支えをしてきたんだろうと思います。わたしたちも、〈ナナロク社〉、〈左右社〉と3社で合同短歌フェアを企画展開するなど、いろいろな取り組みをしてきましたよね。
F.I.N.編集部
今後は、詩歌に携わる編集者としてどんなことをしていきたいですか?
村井さん
これから詩人や歌人の方たちが作品を発表していくうえで、編集者が制作面のサポートはもちろんですが、マネジメント的な機能も求められてくるのかなと感じています。書籍を刊行すると取材や執筆の依頼も相当の数がきます。喜ばしいことではありますが、媒体の大小に関わりなく負担はあり、バランスを崩すきっかけにもなりかねません。謝礼の確認など、得意ではない方も多いですし、また、メディア対応だけでなく、同業の作家とは話しにくい悩みも聞き手として受けとめるなど、役割は様々ですね。
藤枝さん
紙の本は物としてずっと残っていくものなので、できあがったあともその本を届けるためにあらゆることに伴走するというのも出版社の大事な仕事だと思っています。そういう意味では瞬発的なことではなく、本ができる前から、できた後まで長い時間をいかに著者や本と共にあることができるか。いかに未知の読者の方に届ける努力ができるかということを、一緒に色々考えながら精一杯の努力をしていくのが、出版社というものの意義なのかなと思っています。
【編集後記】
これまで詩歌については真正面から触れたことがなかったのですが、村井さん、藤枝さんから魅力を教えていただいたことで、しっかりと触れてみたいと思い、ご紹介いただいた詩集を含めていくつか読んでみました。
詩を読むと自分のことではないのに、なぜだか頭の中で情景を鮮明に思い浮かべられるものがいくつもあり、魅力の一端を感じることができたように思います。
また詩に触れ合っている時間が心に余白を生んでくれるような感覚もおぼえました。まさに情報が溢れる時代になればなるほど、自分に向き合う感覚を生んでくれる時間は大切で、詩という存在がその助けになってくれるのだということを今回身をもって知ることができました。
(未来定番研究所 榎)